この記事を書いているのは6月末。税理士試験まであと2ヶ月を切りました。
今ちょうどT校では全答練が開催されていますね。
私の古巣O原(昔講師をしていました)の全国統一公開模擬試験(全統)は来月の今頃に開催とか。
これから本試験までいろんな答練の問題を解く機会が増えていきます。
手元にどんどん問題が溜まっていって、本試験までにどれを重点的に解くべきか迷うこともあると思います。
そんな「どれを優先して解き直せばいいんだろう」と迷う皆さんに私が強くお伝えしたいのが
「過去問を解くこと」
です!
この記事を書いた人

2007年から2012年まで「資格の大原 税理士講座」で相続税法の常勤講師として勤務。
受験経験者コースを主に担当し、2012年には全国統一公開模擬試験の計算問題の作問も担当しました。
詳しいプロフィール(運営者情報)
税理士試験の勉強方法・攻略法まとめ
目次
ブログ記事の執筆・編集方針及び注意事項(免責事項・著作権など)
カリキュラム上はあまり重要視されていませんが
過去問って、私が講師をしていた頃はどうも存在感が薄い印象でした。
私の頃は、5月の実判期が終わって7月からの直前答練期に入るまでのちょうど今頃の時期に解くカリキュラムになっていたんですが、講師が採点して順位を出すような答練ではないからか、講師の側も解く側もどうもテンションが低い人が多かったような気が…。
「過去問なんて時間の無駄だから解かない」なんて言っていた講師もいました。
そんなんして自宅で解く人なんてほとんどいないのにアホちゃうか?と思っていましたが…。
過去問は実はメチャクチャ重要な答練なんですよ!
なぜなら、「本試験の問題に慣れることができるから」です。
本試験の問題に慣れることがなぜ重要なのか、その理由は2つあります。
理由その1:試験委員は過去問を見て本試験を作成するから
税理士試験の国税(法人、所得、相続、消費など)の税法科目の試験問題は、理論は国税庁の担当課の課長、計算は実務家(税理士)が作成します。
講師をしていた頃に目にした情報(注:今からだと15年以上前の古い情報です)によると、計算問題の試験委員を担当すると決まった場合、国税審議会からその先生の事務所に向けて
「問題はこれを参考に作って下さい」
という感じで過去のその科目の本試験問題がどっさりと送られてくるんだそうです。
そして、試験委員の先生はそれらの問題を見て本試験の問題を作成されるとか。
「敵を攻めるにはまずは敵を知ることから始めるべし」です。
試験委員が問題を作るにあたって参考にしているものを解いておかないわけにはいかないでしょう!
問題は3月にはほぼ出来上がっている!?
ちなみに、先日過去試験委員をされていた某先生からお酒の席で(笑)ちらっと伺ったところによると、その先生が担当されていた頃は本試験の問題は3月頃に理論の作問者(相続税法なら資産課税課の課長)の部下さんと問題のすり合わせをしていたそうです。
その時点でその部下さんに問題をザッと解いてもらった、と仰っていました。
つまり、以前「税理士試験の試験委員が発表、で思い出す講師時代の痛い経験」という記事で
「5月の税理士分科会の頃には問題もほぼ完成しているはず」
と書きましたが、あの読みはやはり合っていて、3月の時点では既におおよその問題が出来上がっているようですね。
その時点では専門学校の直前答練なんてあるはずも無いわけで、
そう考えても、試験委員が問題作成の参考にする資料はやはり過去問しか無いということになります。
理由その2:本試験の問題はいつも解いている問題とは少し雰囲気が違うから
あと、過去問を解いた後って、いつもとはちょっと違う疲れが残りませんか?
見慣れない様式や出題方法など、いつも解いている問題と雰囲気が少し違うのがその原因です。
大雑把な言い方をすれば、いつも解いている問題よりも少し荒削りな感じがしますよね。
専門学校で解く答練も、直前答練ぐらいになると過去問を真似て作ります。
ただ、たとえ一番最初に作問者が作った時点ではゴツゴツとした荒削り感が出せていたとしても、初校、二校、三校と校正を重ねるごとにそんな荒削り感もだんだんと削られていってしまいます。
結果、できたものは他の答練と見た目もそんなに変わらないという(^^;
教材として出す以上、どうしても無難なものにならざるを得ないんですよね。
でも、本試験の問題は何人もの目を通すまではさすがにしていないでしょうし(もししていたら数年前の固定資産税みたいなハチャメチャな問題なんて出るわけないですし)、荒削り感はどうしても残ります。
そんな本試験の出題様式を体に覚えさせるためには、過去問の解答がやっぱり一番効果的です。
過去問を解いていなかったことで失敗したあの年
私も、受験生としての最初のうちは過去問の存在はハッキリ言って軽く見ていました。
ただ、消費税法と所得税法を受けた年に、消費税法こそ運良く受かったものの、初日のその消費税法で燃え尽きてしまって次の日の所得税法(どちらかといえばこっちの方が本命でした)でケアレスミスを連発して落ちる、という経験をしました。
なぜ燃え尽きたのかというと、消費税法の本試験の問題に慣れていなかったからです。
この年、私は消費税法は初受験でしたが、それまでの成績は全然良くなかったですし、なんとか本試験に間に合ったというような状態でした。
過去問を解く余裕が全くなかったことで、本試験の問題に慣れていなかったことが本試験後の疲れを増幅させて、結果、翌日は腑抜けの状態で受けることになってしまったんだと思います。
(しかも、問題を解いている時はそれに全く気付いていなくて、あとで見直して初めてケアレスミス連発に気付いたんですよね…。)
翌年からは、直前期の勉強方法も過去問重視に切り変えて、最後の数日は総合問題は過去問しか解かない、という形に変えました。
今年初受験の科目を受けられる皆さんには、↑こうならないためにも過去問をしっかりと解いておくことを特にオススメします!
知らない論点には惑わされないように!
ちなみに、過去問を解いていると今まで見たことが無い論点がいっぱい出てきます。
「こんなの解けなあかんの?うげぇ〜。」
って思うかもですが、忘れてはいけないのは本試験で重要なのはAランクがどれだけ解答できるかです。
過去の↓この記事でもそのことについて詳しく触れています。
過去記事税理士試験合格に必要なのはAランク(基本論点)を合わせる力
過去問を解く理由は、あくまでも本試験特有の荒削りな問題の雰囲気に慣れるためです。
過去に出ている論点を丸々無視するのも良くないですが(特に相続税法は過去の出題論点は当たり前のように出されることも多いですし)、あまりそこばかりを追いかけるのも得策ではありません。
大切なのは基礎固めを忘れないこと。
そこは見失わないように、今後の勉強を進めていって下さい!
以上、この記事では
「本試験を攻略するには過去問は絶対に外せない!」
というお話をお送りしました。
【関連記事】
- 「会計人コース」さんに過去問の有用性について執筆・寄稿しました!
過去問を120%活用して税理士試験合格を勝ち取ろう【会計人コース2019年5月号寄稿】 - 【税理士試験】受験8年間で冒した3つの失敗を振り返る
- 税理士試験合格に必要なのはAランク(基本論点)を合わせる力
- 税理士試験まであと1ヶ月。これからの時期にやるべきこと
- 税理士試験の合格答案の書き方。他の答案と差別化が図れる6つの方法
私自身の合格体験はもちろん、講師時代に得た経験や情報をぎゅぎゅっと凝縮しました。
税理士試験の勉強方法・攻略法のまとめ【元O原講師が綴る】へ

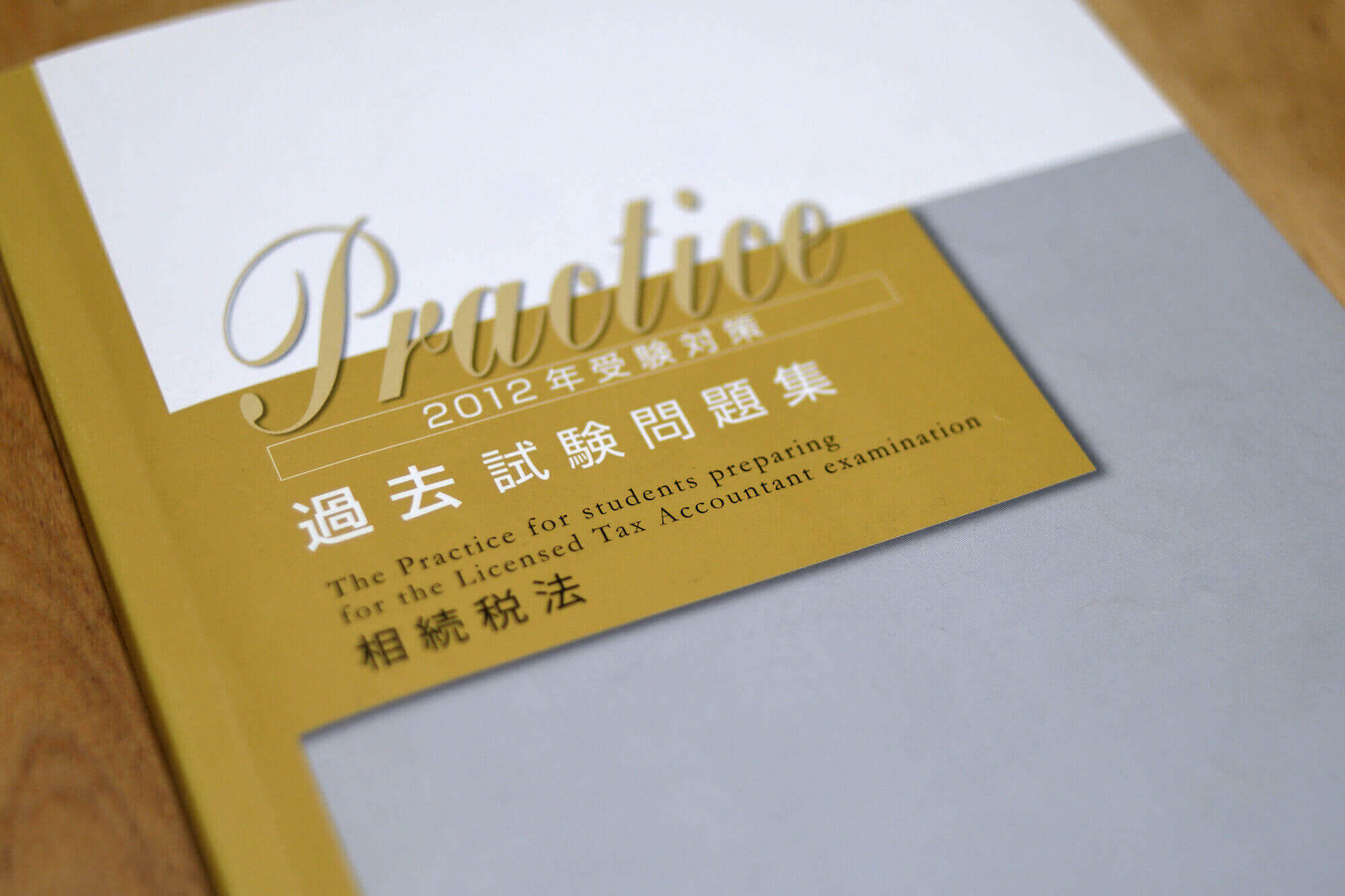
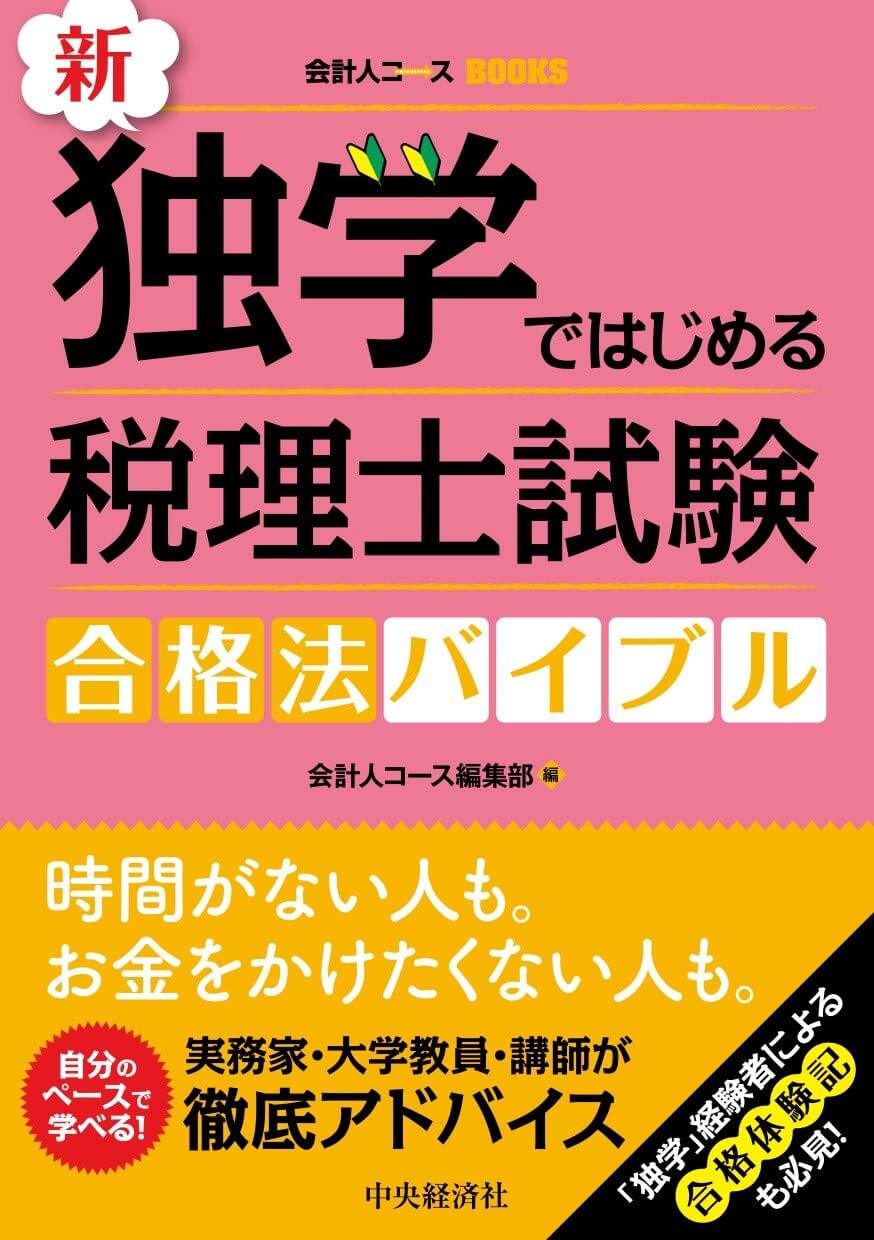

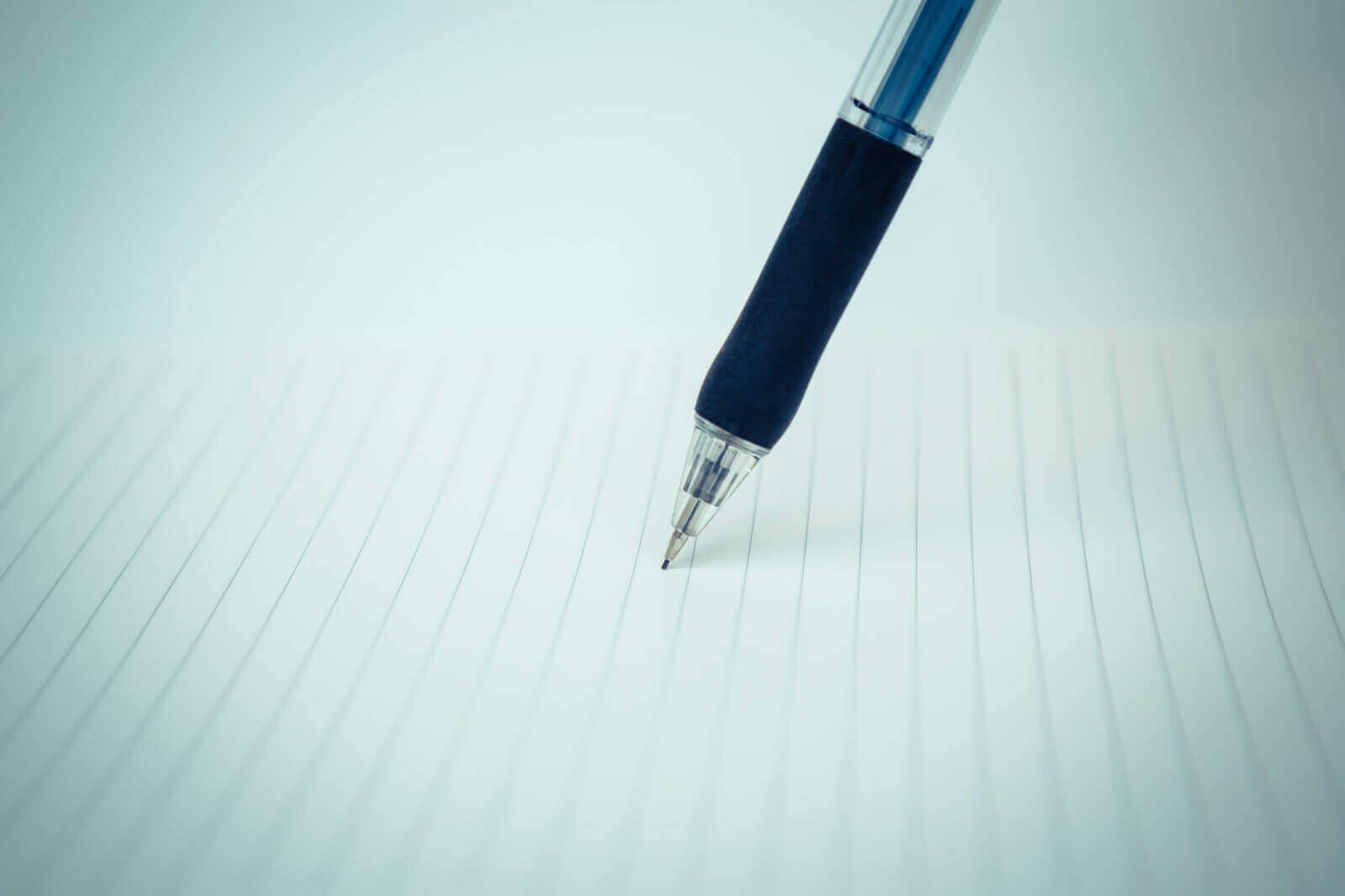

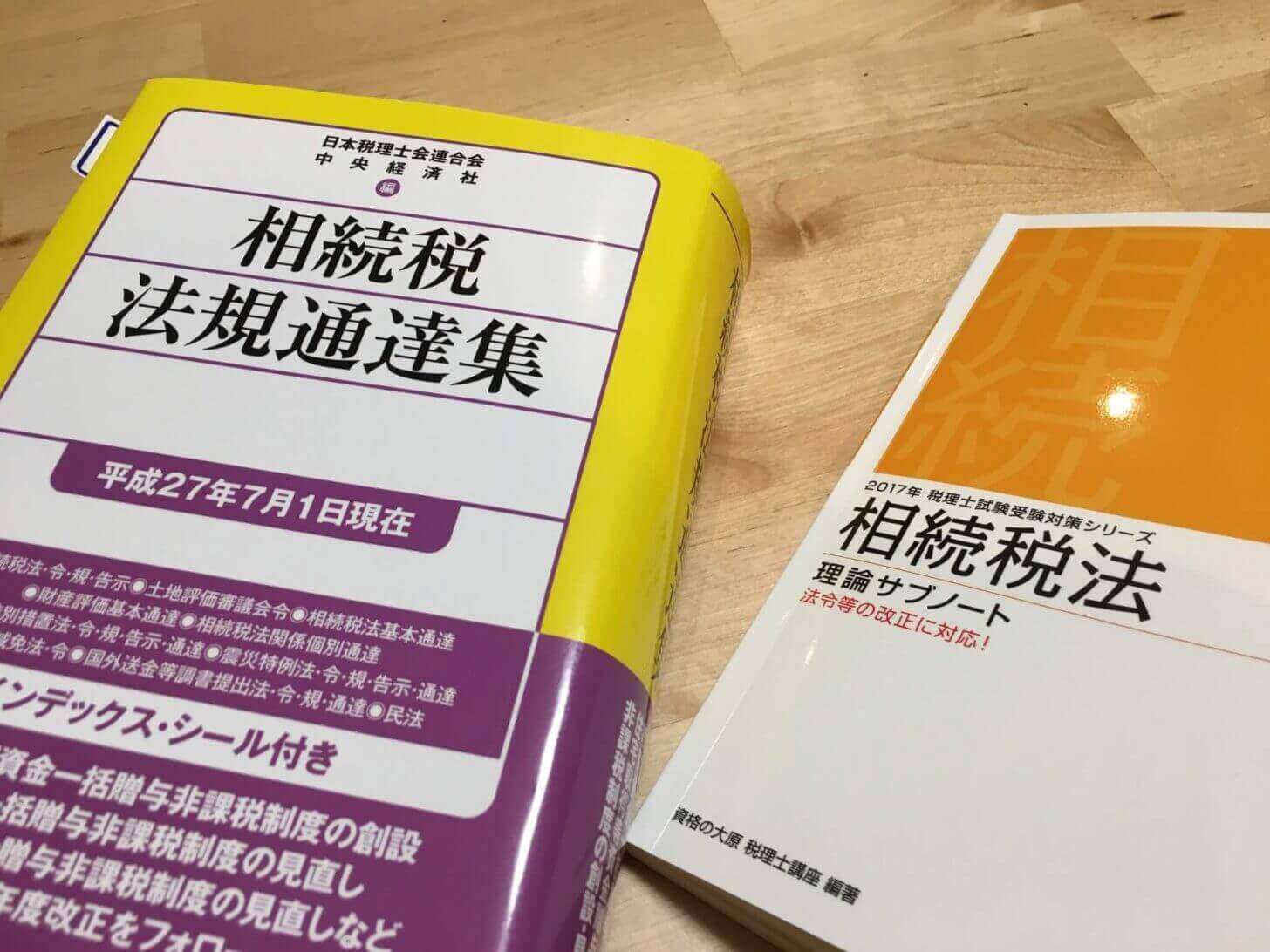

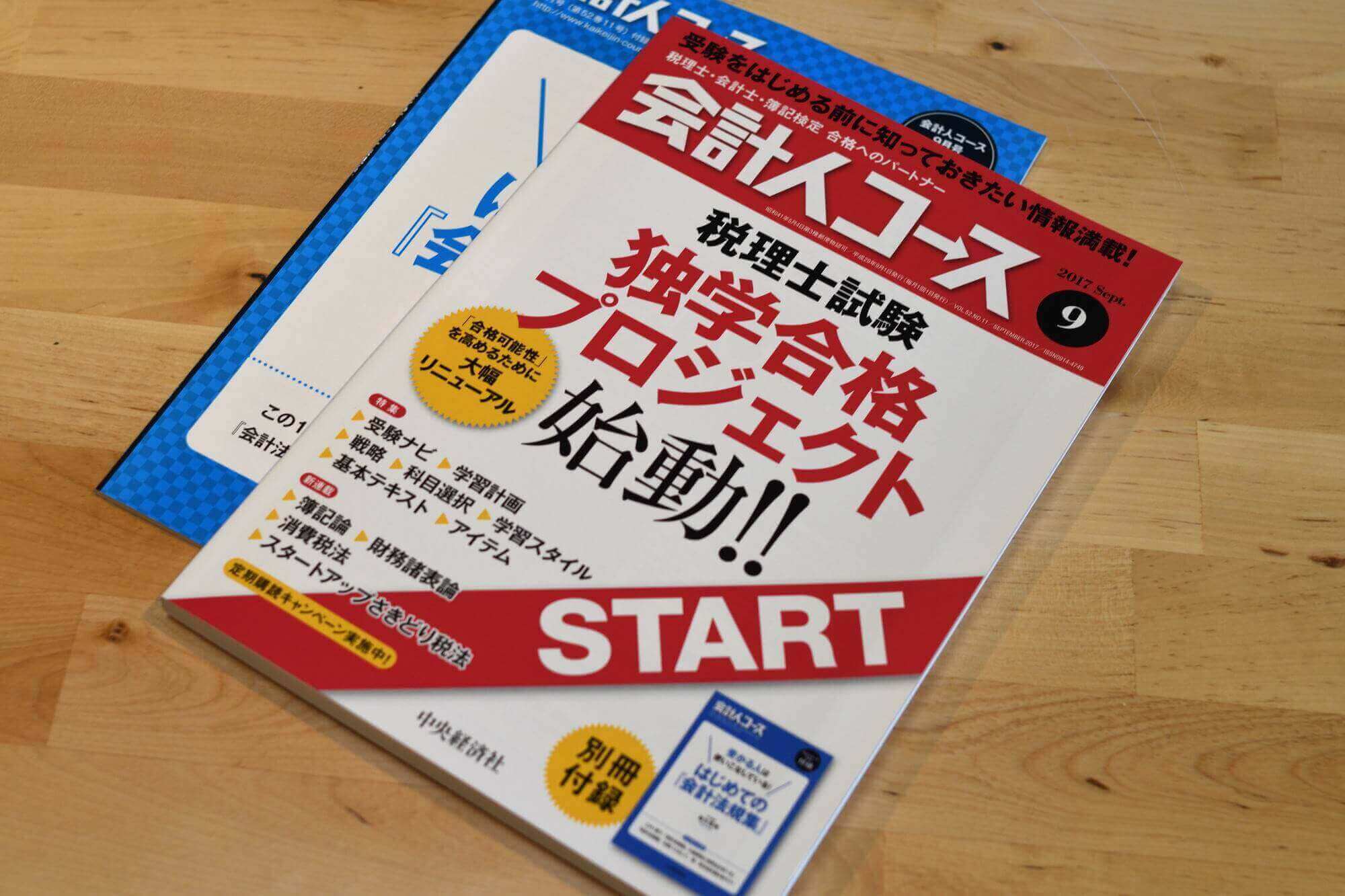


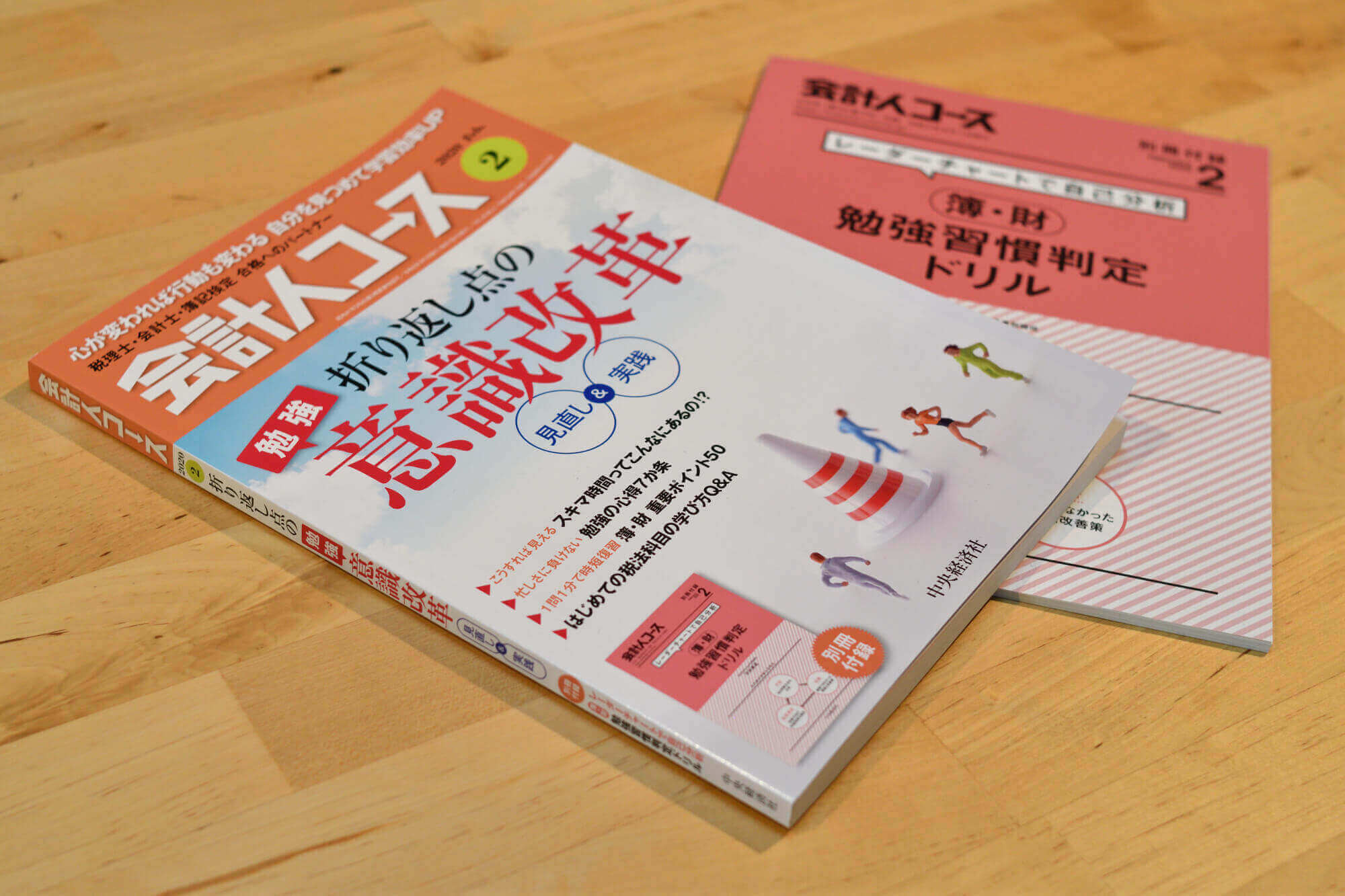
詳しくはこちらの記事で晒しています…。
【税理士試験】受験8年間で冒した3つの失敗を振り返る