↑これ、税理士講座講師時代は授業で言いまくっていました。
「自分が何書いてるかなんて答案見ればわかるやん?そんなん書いてる時間ももったいないし!」
とお思いの受験生の皆さんにこの記事を贈ります。
この記事を書いた人

2007年から2012年まで「資格の大原 税理士講座」で相続税法の常勤講師として勤務。
受験経験者コースを主に担当し、2012年には全国統一公開模擬試験の計算問題の作問も担当しました。
詳しいプロフィール(運営者情報)
税理士試験の勉強方法・攻略法まとめ
ブログ記事の執筆・編集方針及び注意事項(免責事項・著作権など)
ベタ書き問題はまだまだ多いです
近年の税理士試験の出題傾向を見ると、規定をそのまま書く、いわゆる「ベタ書き問題」の出題はだんだん少なくなくなってきています。
法人税法なんか、最近は2問とも事例形式での出題が当たり前ですもんね。
ただ、私が担当していた相続税法に関していえば、ここ数年を見ても未だに
- 問1は規定のベタ書きを要求する問題
-
問2は事例形式っぽい(←あくまでも「っぽい」)問題
という出題パターンが続いています。
ベタ書き問題も科目によってはまだまだ生き続けているんです。
そんな問題が出題されたときは、問いに当てはまる規定をただ羅列して解答しがちですが、ここでひと工夫を加えるだけで他とは違うキラリと光る答案を作ることが可能になります。
その工夫の1つが今日紹介する↓コレです。
「ベタ書き理論を解答するときこそ必ず最初に結論を書くべき!」
やり方は簡単です
「そんなん言われてもどんな書き方をすればええねん?」
と思われるでしょうが、やり方はとても簡単です。
ベタ書きする解答の一番最初に〔1〕概要とタイトルを付けた上で、
本問においては●●、▲▲、□□の3つの規定が該当する。
と、これから書く規定の内容をリストアップするだけです。
たったそれだけで、採点する側の受ける印象も大きく変わります。
狙うのは「印象点のアップ」
最初に結論を書くことによって得られるメリットはただ1つです。
それは「印象点のアップが狙える」こと。
「たったそれだけ??」
と思うでしょ?でもそれがバカにならないんです!
私も元講師として大量の答案を何度も採点してきたのでよくわかりますが、答案の採点ってメチャクチャ大変です(^^;
私なんて多くても全クラスでたかだか100人程度でしたが、たったそれだけの理論の採点だけでも、どれだけ気合を入れてエナジードリンクを飲みまくって隔離部屋に閉じこもってやっても(笑)丸1日は絶対にかかりました。
それが、本番の税理士試験は相続税法だけでも受験者が3,895人(昨年の数字)。
しかもそれを最長でも2ヶ月の間に全て採点し終えるといいます。
60日間毎日ひたすら採点したとしても、1日あたり64人分??
そんな採点者(の人達?)に対して受験生の方がまず心掛けるべきなのは、
「採点するときに採点者に自分が何を書いているのかを探させるような答案は書かない!」
ということ。
向こうはなるべく早く採点を終わらせたいんですから、そんな向こうの姿勢に協力するような答案を書くべきですよね。
「この答案にはこれこれこれが書いてあるんですよ」
と最初に示してあげることも採点しやすい答案を作る作業の一環なんです。
あと、世の中に目次が無い本なんてありませんよね?
目次を見ればその本に何が書いてあるのかもだいたいイメージできます。
(ブログで言えば見出しですね。)
理論の答案もそれと同じで、「目次」があるだけで採点者からの見た目は相当違って見えますよ。
興味が無い採点者には「初頭効果」を狙うべし
また、心理学の世界で「初頭効果」と「親近効果」いう言葉があるんですが、結論を最初に書くことでこれらのうちの「初頭効果」が狙えます。
両者をわかりやすく解説してくれているブログの記事を見つけたので紹介します。
初頭効果は物事の最初が印象に残りやすい現象のことで、
親近効果は反対に一番最後が物事の印象に残りやすい現象です。(中略)
関心の薄い顧客に対しては初頭効果、
逆に関心の高い顧客には親近効果、
という形がベストです。関心が薄い顧客へは最初でガツンとインパクトを与えないと
そのまま去ってしまうわけですから、
それを繋ぎ止めるには出し惜しみはできません。一方ある程度関心の高い顧客に関しては、
相手の興奮を販売の局面で最高潮にするために、
一番重要な情報を最後に持って来ます。引用元:初頭効果と親近効果の違いと使い分け。どちらが重要?(リンク切れ)
ここで質問ですが、理論の答案って採点者にとって関心の高いものでしょうか?それとも薄いものでしょうか?
そんなの、薄いに決まってますよね。
「こんなんはよ終わらせたいわ〜」と思いながらやってるに決まってます(^^;
ただでさえ、ベタ書き問題の答案は規定を羅列したものばかりが並びがちです。
そんな中、最初にガッツリと結論が書いてある答案がパッと出てきたらどうなるでしょう??
「お、こいつはちょっと違うかも?」
そう思わせた上でさらに柱がちゃんと挙がっていれば、多少中の規定を端折っていたとしても
「はいはい、この人は分かってる人〜。」
とすんなり採点してくれるかもしれません。
てか、そうでもしないと終わる採点量じゃないですからね。
「してくれるかもしれません」じゃなくて「してくれます」と断言しても大丈夫かもしれません。(って、断言できてないし(^^;)
最後に結論を書くのもいいかもしれませんが、それもあくまでも
「興味を持って見てくれた答案の最後の一押し」
として効果があるぐらいです。
最後に書くぐらいなら最初に書いてしまいましょう。
まとめ 「採点者ファースト」の答案作りを!
今日記事にした内容は
「自分の答案をより良く見せるためのテクニックの1つ」
です。
税理士試験では
「私はこの試験に合格する力があるんですよ」
ということを答案を通じて採点者にアピールすることが何よりも必要です。
そこで心掛けるべきなのは、モバイルファーストならぬ「採点者ファースト」な答案を作ることです。
自分本位の答案ではせっかく実力があってもアピール力は弱くなります。
上で紹介したようなほんの少しの努力で受け手側の印象は大きく変わります。
「受かる実力はあるはずなのにあと一歩何かが足りない…。」
というような方は是非「採点者ファースト」な答案作りを心掛けてみればいかがでしょう?
何が合格を左右するかわかりません。
1点が合否を左右する世界ですから、不確定要素はなるべく排除するように努めるべきです。
もちろん、いくらアピール力が高い答案でもその結論自体が間違っていては効果が無いので、正確に柱挙げができるようにすることもお忘れなく(^^)v
本試験まであと2ヶ月と少し。
この記事を見に来た皆さんの本試験での成功を祈ります!
【関連記事】

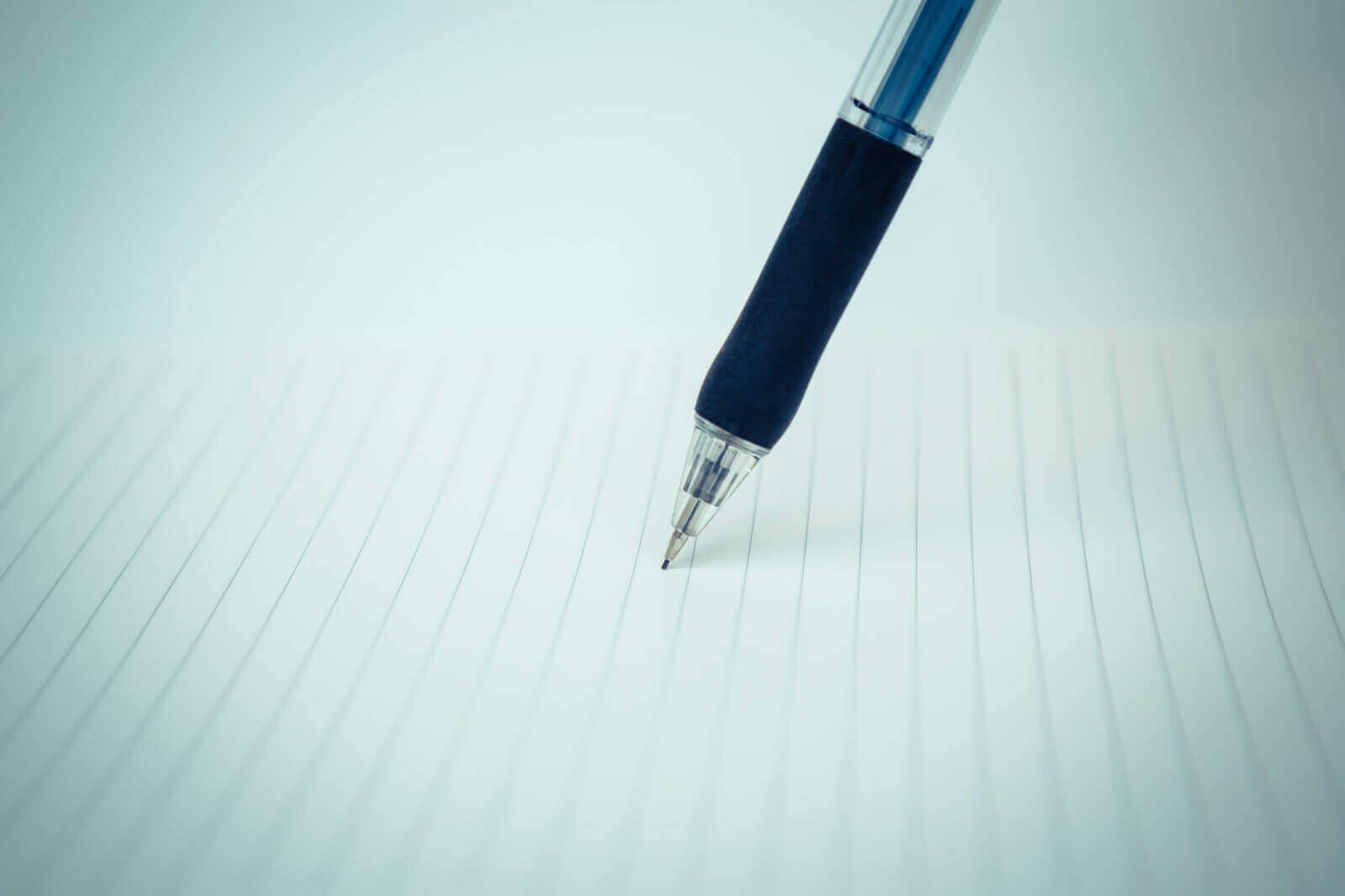
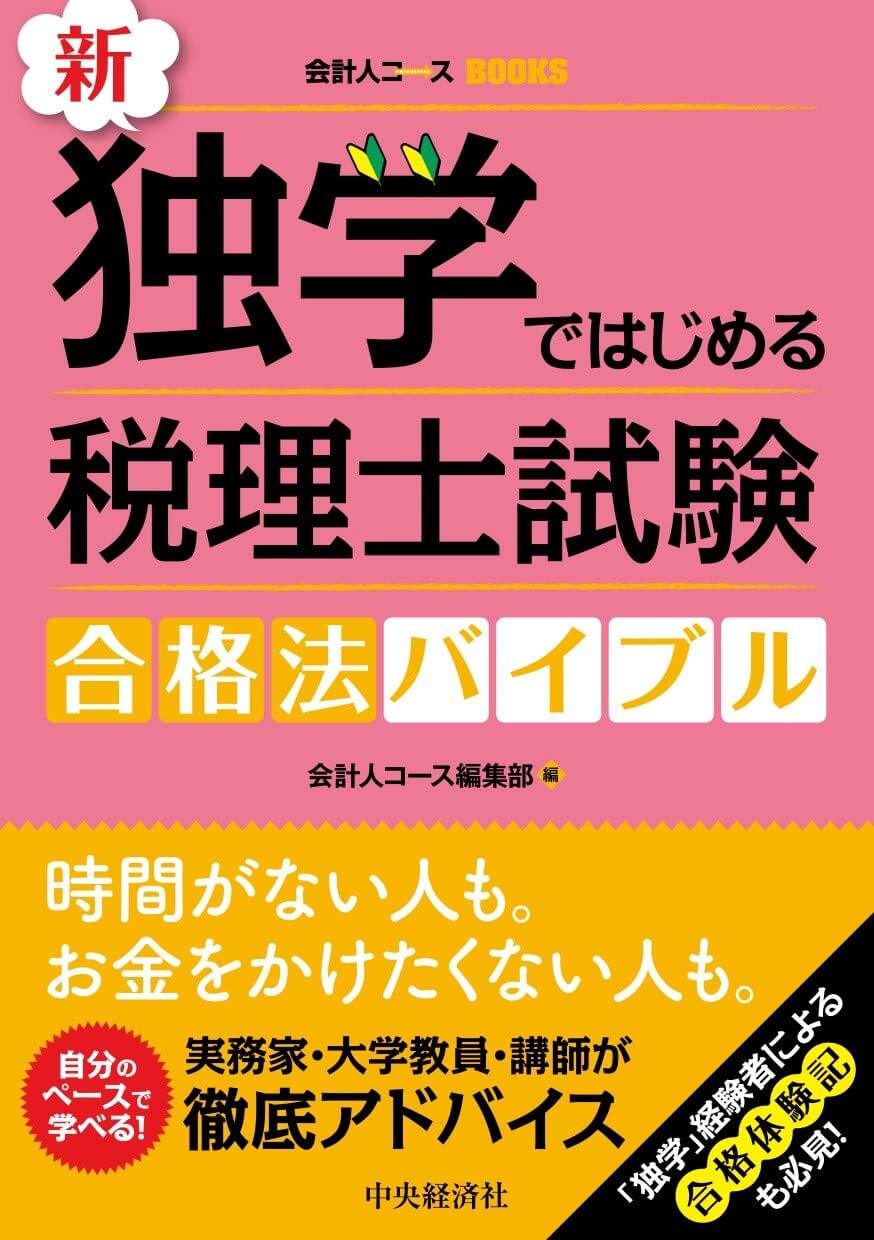

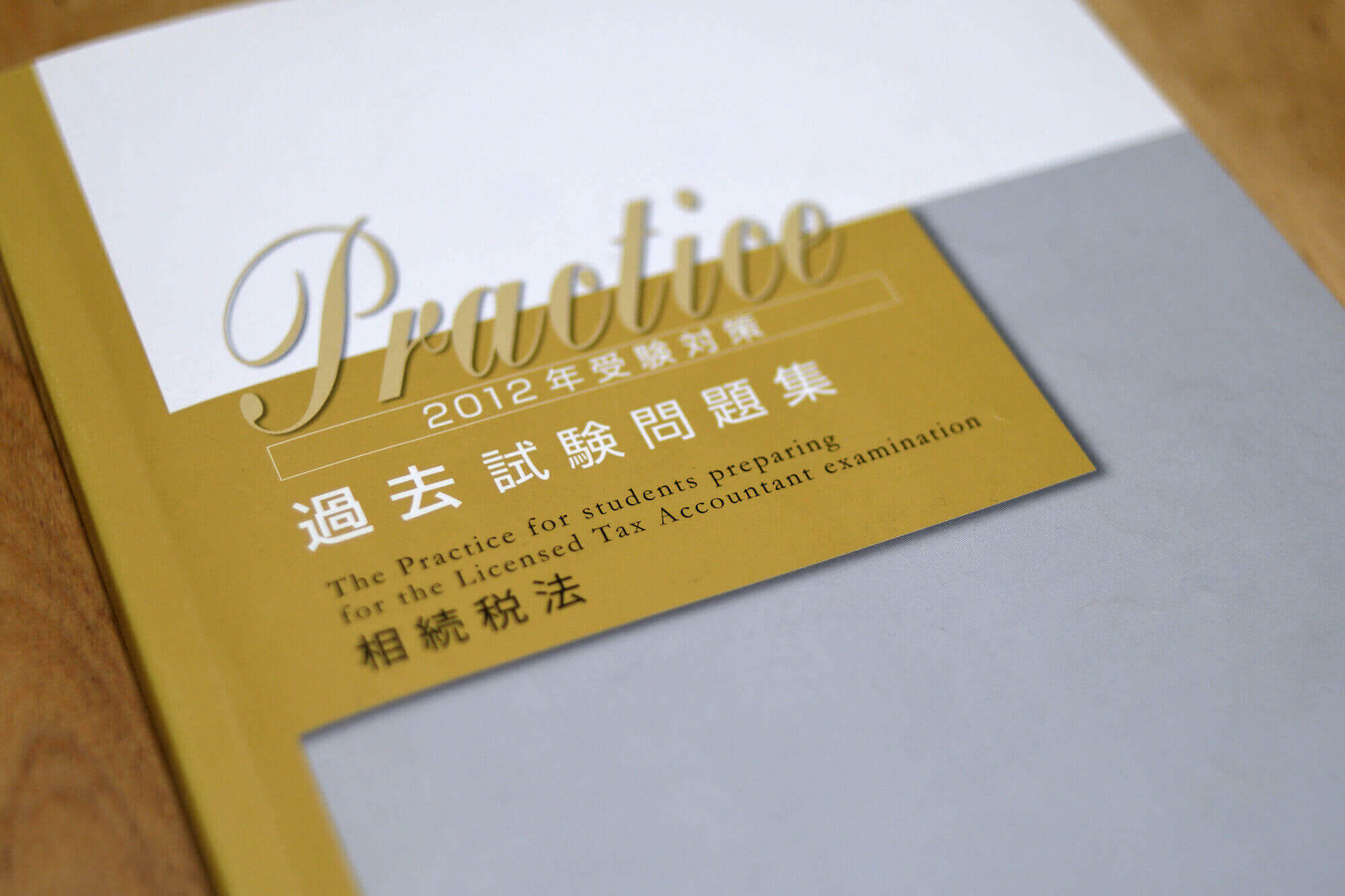

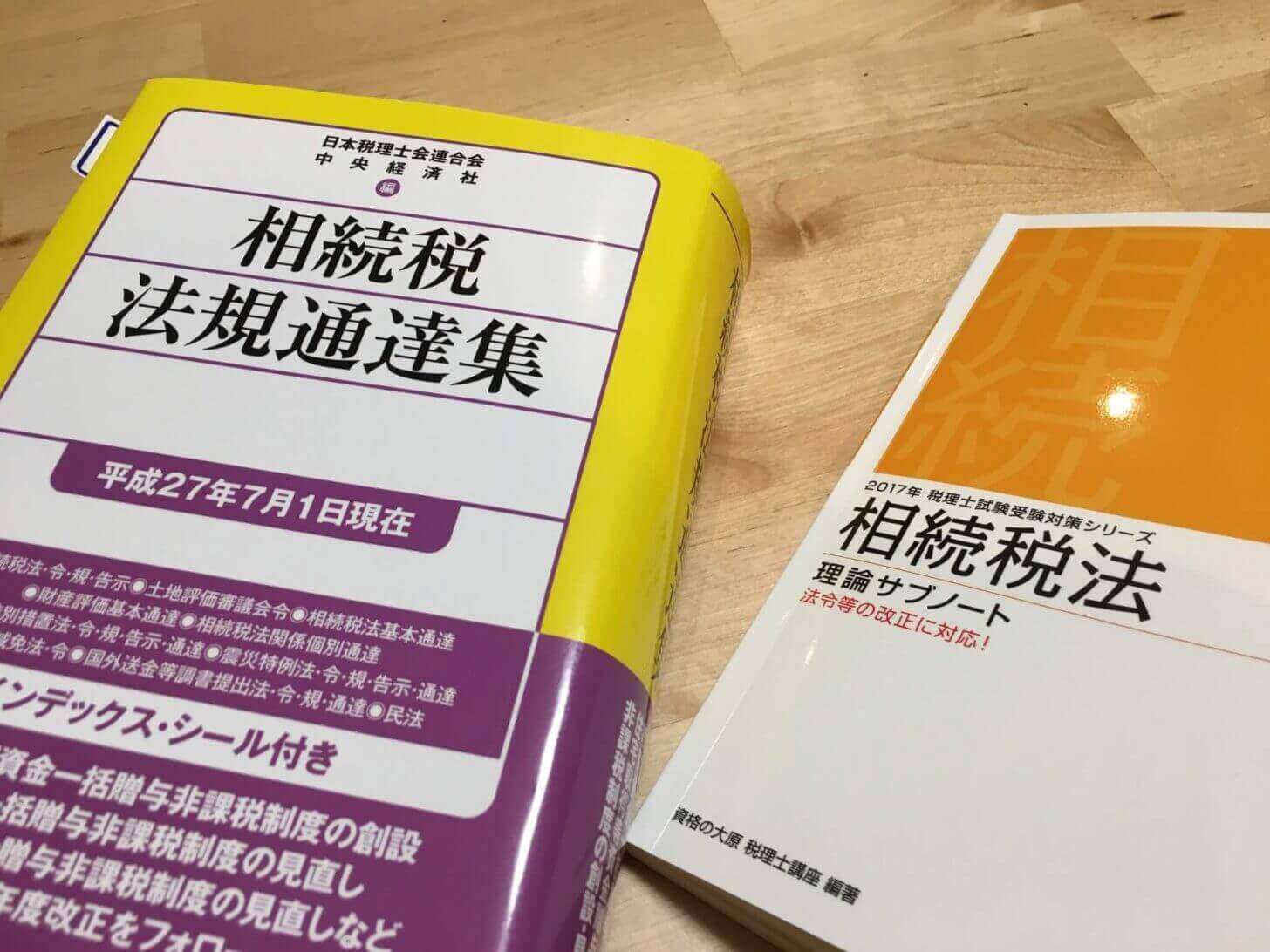

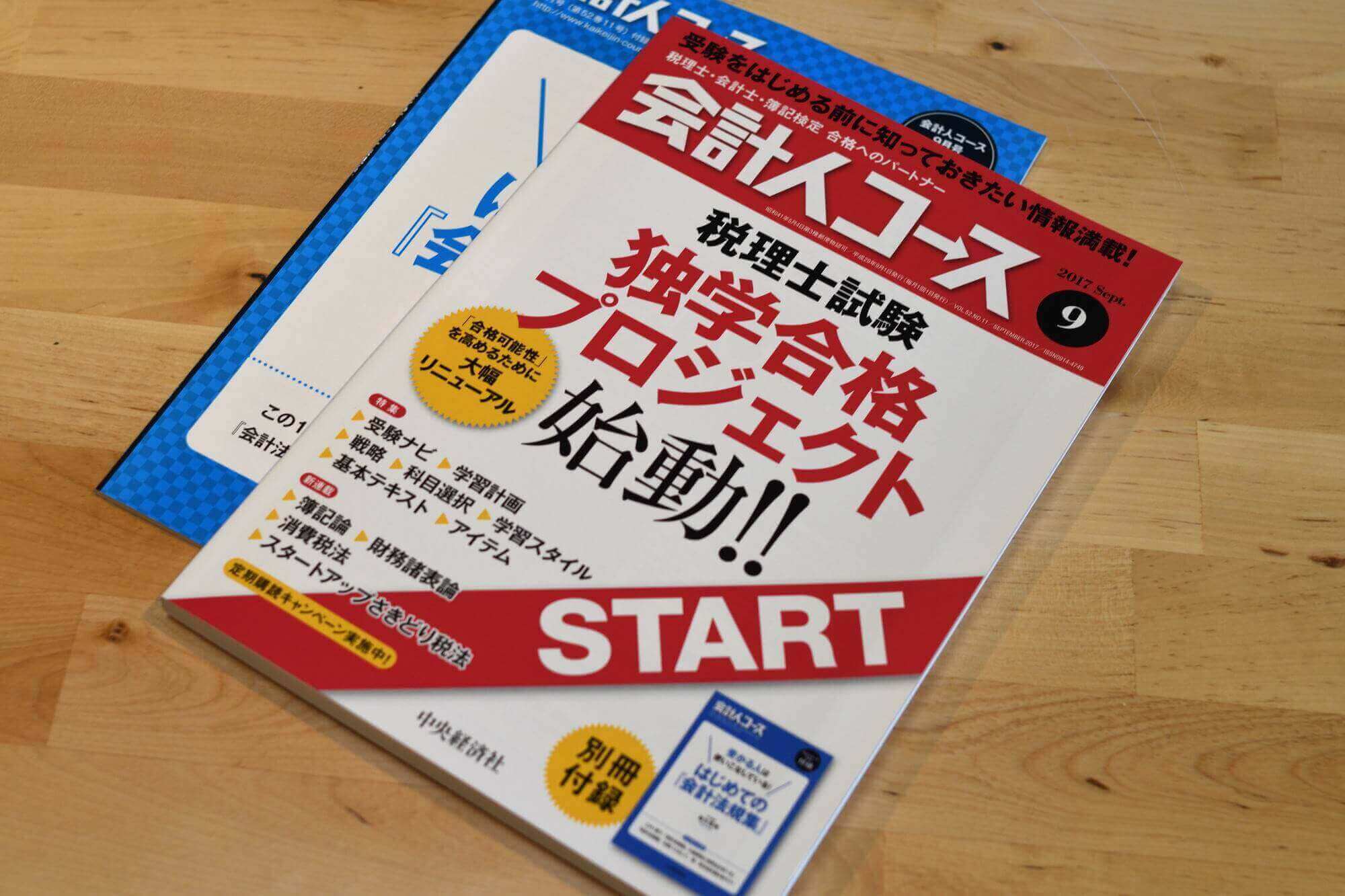


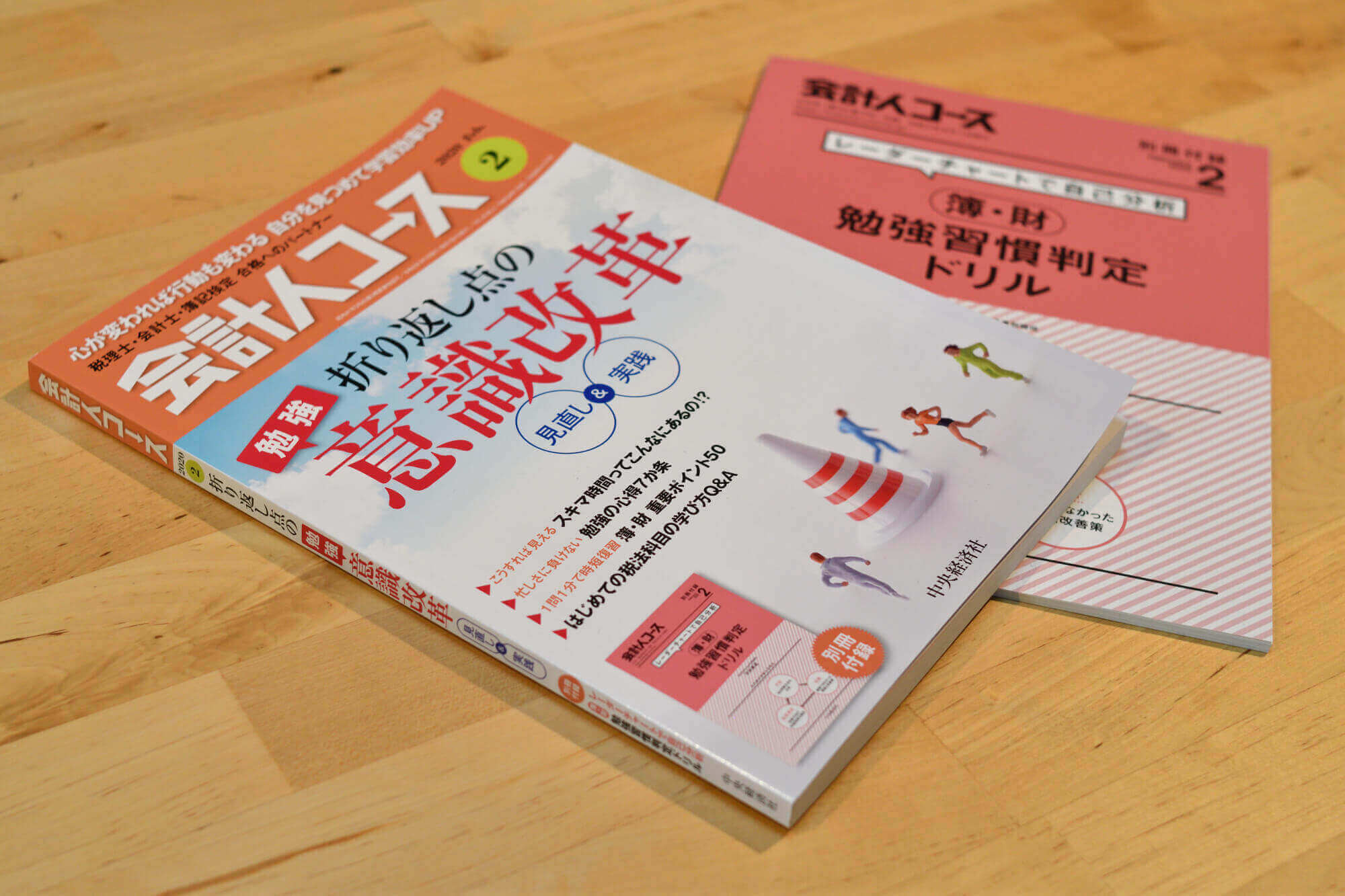
私自身の合格体験はもちろん、講師時代に得た経験や情報をぎゅぎゅっと凝縮しました。
税理士試験の勉強方法・攻略法のまとめ【元O原講師が綴る】へ