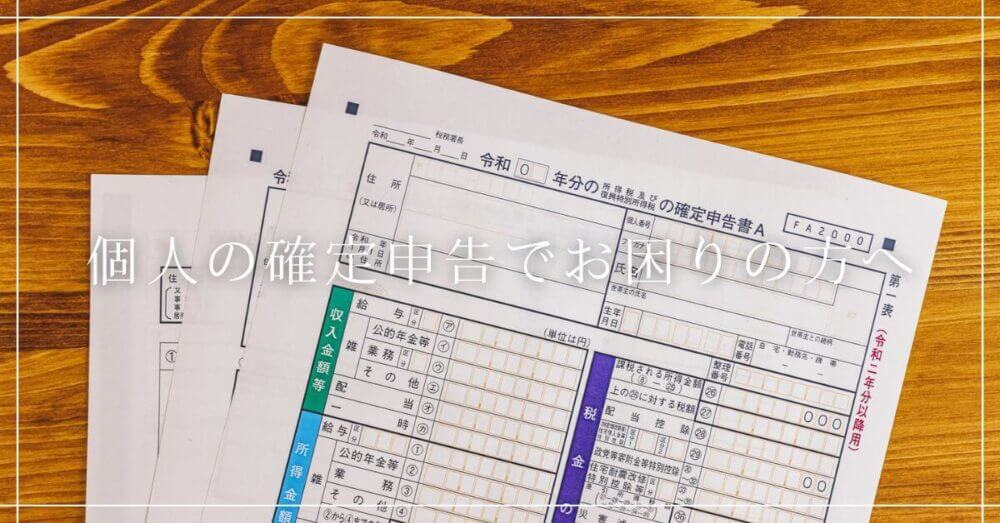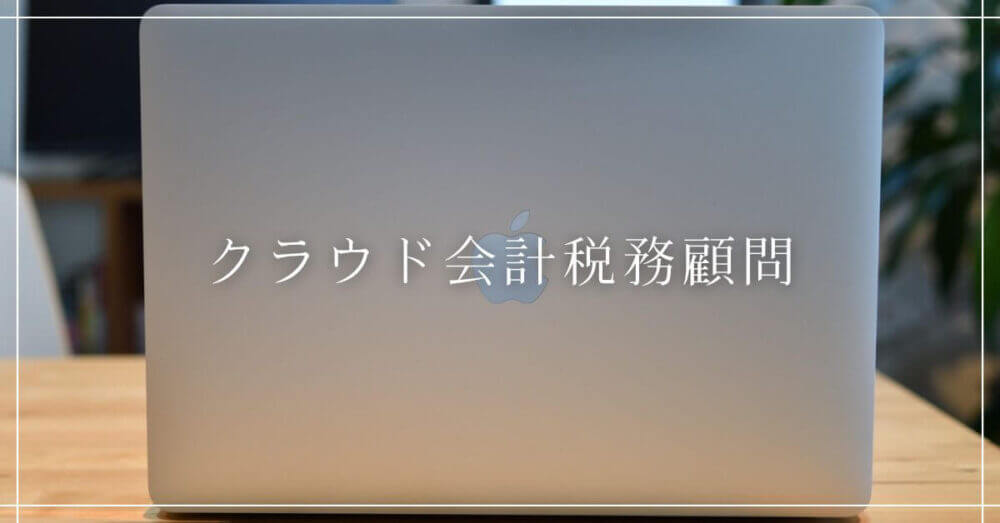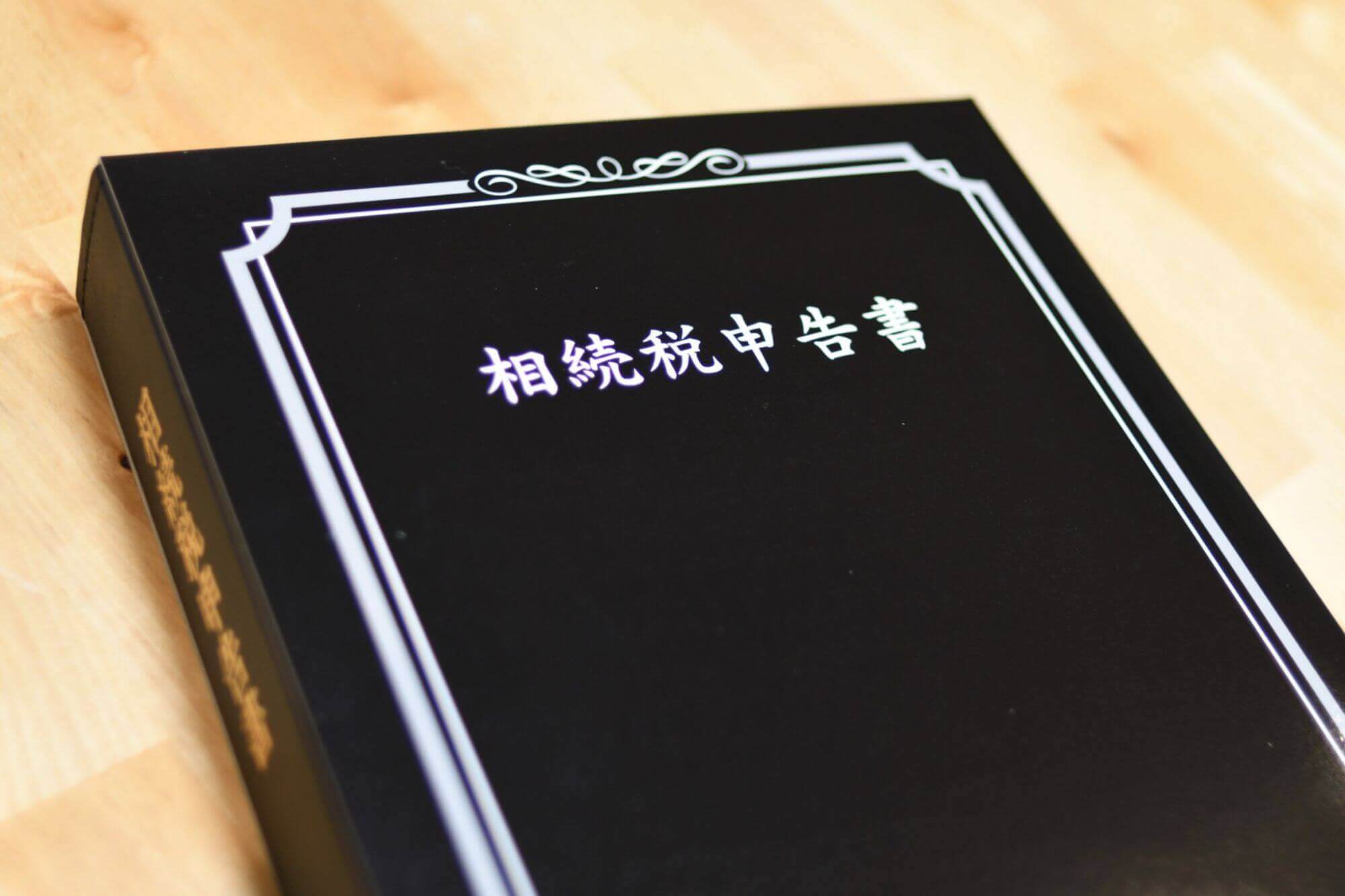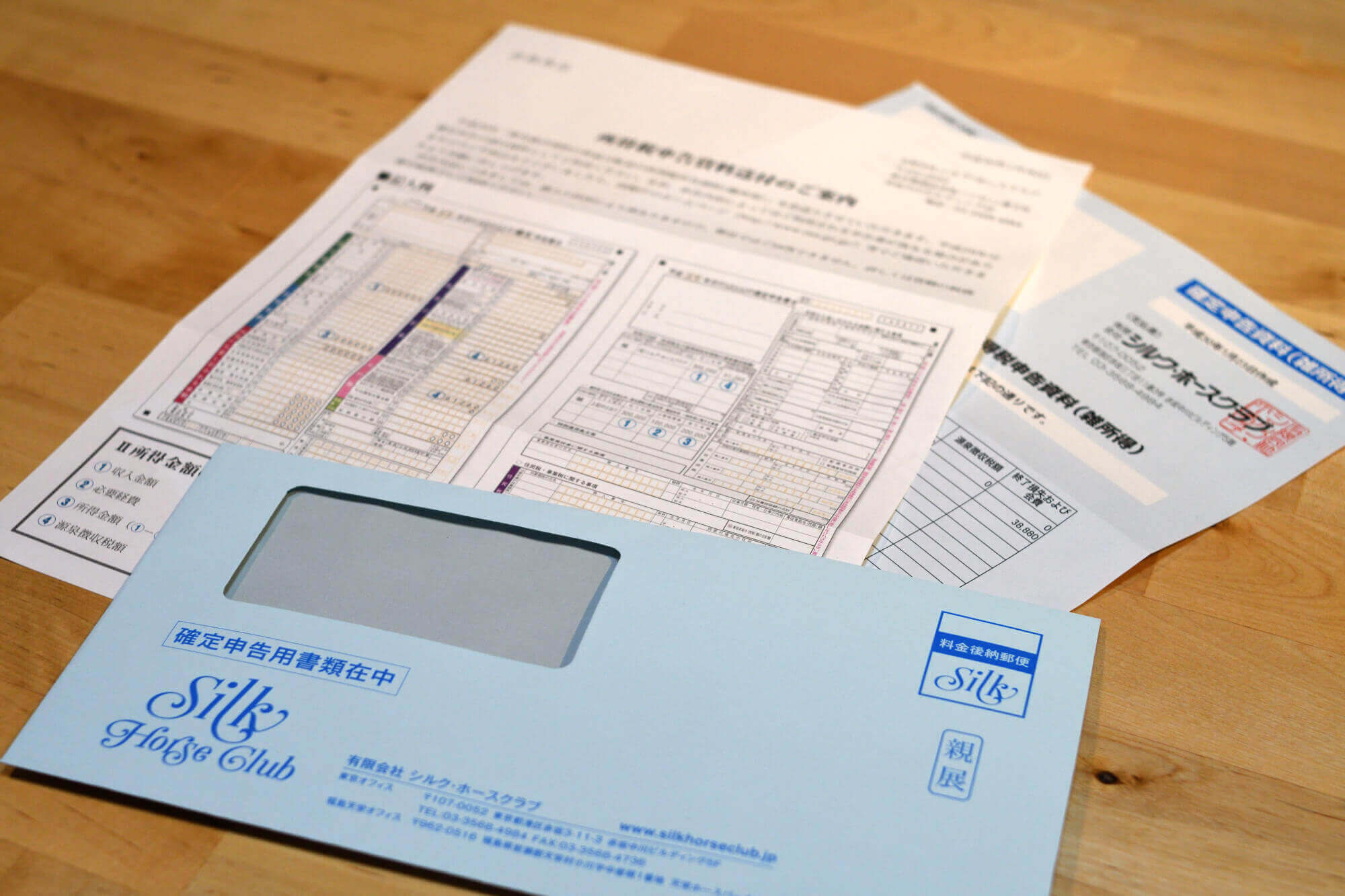よく「源泉徴収」という言葉を耳にしますが、これって具体的にどんな制度か皆さんご存知でしょうか。
また、私自身、源泉徴収をしなければいけないのにしていない取引を見かけることも多いです。
そこで、今回から全5回に分けて、この源泉徴収制度について、
どんな制度で、誰が、どんな金品のやり取りについてしなければいけないものなのか
をいろいろとまとめてみます。
第1回目の今回のテーマは「誰が源泉徴収しなきゃいけないの?」です。
- 源泉徴収義務者とは?こんな人は源泉徴収が必要です(←今はここ)
- 源泉徴収の対象となる所得には何がある?
- 源泉徴収税額はいくらにすべき?【源泉徴収税率のまとめ】
- 報酬や料金の源泉徴収税率は何%?【種類別に紹介】
- 【源泉所得税の納付期限】原則と納期の特例の違いとは?
- 中途退職者に給与の源泉徴収票を発行する場合の4つの注意点
この記事を書いた人

税理士試験大手予備校の元講師で、事務所開業後は所得税などの研修会講師を数多く担当。
Macユーザーで、クラウド会計を活用したスモールビジネス支援にも力を入れています。
詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)
- 「確定申告をお願いしたい」という方へ
確定申告代行(決算込み) - 「わからない点を単発で相談したい」という方へ
単発スポット相談 顧問税理士はクラウド会計をお使いの方限定でお受けしています
クラウド会計税務顧問
当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。
当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。
ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)
このページの目次
【前提】源泉徴収制度ってどんな制度?
本題に入る前に、まずは「源泉徴収ってそもそもなんであんの?」という話からしておきましょう。
我々国民はみんな納税の義務を負っていますが、
所得税では、我々自身がいくら税金を払うかを計算して、それを申告して国に納付するのが原則です。
(これを「申告納税制度」と呼んでいます。)
ただ、所得税について完全にこの方法だけにしてしまうと、
- サラリーマンも含めたすべての方が確定申告をしなくちゃいけなくなる(確定申告の時期は今以上に混乱すること必至!)
-
取りっぱぐれがとてつもなく増えそう?(+それを捕捉するのも大変)
など、運用上のデメリットが大きいので、
給与や報酬など、一部のお金のやりとりについては、その支払いの際に、支払いをする人が仮払いの所得税(源泉所得税)を徴収して国に納付し、支払いを受ける人はその残額のみを受け取ることになっています。
これが「源泉徴収制度」です。
ただ、これを半年に1回に出来る特例もあります。
(詳しくは「【源泉所得税の納付期限】原則と納期の特例の違いとは?」という記事で紹介しています)
源泉徴収は原則「支払いをする人すべて」が行う
上を踏まえて、本題である「誰が源泉徴収しなきゃいけないの?」という話に移ります。
この源泉徴収は、原則、給与や報酬などの支払いをするすべての人が行う義務があります。
個人、法人、特定の団体、官公庁問わずです。

そう思われた皆さん、ご安心下さい(^^
あくまでも「原則」なので、以下に該当する方は源泉徴収をする必要はないとされています。
個人は全員が対象ではありません
国税庁のHPにこんな文言が挙がっています。
個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)
給与や退職金を支払っていない個人は源泉徴収不要!
つまり、個人で
- 家のお手伝いさんにだけ給与や退職金を払っている
-
給与や退職金自体誰にも払っていない
上のいずれかに該当する人は、いくらどんな目的で税理士などに報酬を払おうが、それに対して源泉徴収をする必要はありません。
逆に言うと、
個人であっても誰かに給与や退職金を支払っている人は、
その給与や退職金自体に源泉徴収税額があろうが無かろうが、
税理士などに支払う報酬について源泉徴収をする必要があります。
青色事業専従者給与を払っている方はもちろん源泉徴収が必要です
ここで言う「給与」には、配偶者や家族に支払う「青色事業専従者給与」ももちろん含まれます。
上に書いているとおり、誰かに給与を支払っている人はその給与自体に源泉徴収税額があろうが無かろうが源泉徴収をする必要があります。
家族1人に対する毎月の専従者給与の支給額が88,000円未満の方は、その給与から源泉徴収をする必要はありません。
でも、「誰かに給与を支払っている」という事実は変わりないので、他に税理士などへの報酬の支払いがある場合には、その報酬に対して源泉徴収をする義務が生まれます。
ここ、専従者給与を支給されている方は忘れがちな点ですので気を付けましょう!
源泉徴収義務違反には利子+罰金のペナルティが
源泉徴収をしなかった場合や源泉徴収した税額の納付が漏れていた場合、源泉徴収義務者に対して次のようなペナルティ(利子+罰金)がかかります。
加算税の一種で、源泉所得税に対してのみ設けられているものです。
納期限(原則翌月10日)に遅れた場合、納付額の5〜10%が加重されます。
ただし、期限から1ヶ月以内に納付して前科(?)も無い場合には免除されます。
納期限の翌日から実際に納付した日までの日数に応じて課される利子です。
たとえ、相手から受け取った報酬の請求書に源泉所得税の記載が無かったとしても、自分自身が源泉徴収義務者である方は、報酬などを支払う際には源泉徴収をする必要があります。
そして、源泉徴収が漏れていたことによってペナルティを受けるのはあくまでも支払いをする側のみです。
報酬を請求する側も、相手が源泉所得税の徴収漏れを起こさないように、請求書を発行する際には相手が源泉徴収義務者にあたるかどうかの確認は忘れないようにしたいものですね。
次の記事では、この記事を踏まえて、
「どんな種類の金品のやり取りについて源泉徴収をしなければいけないのか」
について見ていきます。
- 源泉徴収義務者とは?こんな人は源泉徴収が必要です(←今はここ)
- 源泉徴収の対象となる所得には何がある?
- 源泉徴収税額はいくらにすべき?【源泉徴収税率のまとめ】
- 報酬や料金の源泉徴収税率は何%?【種類別に紹介】
- 【源泉所得税の納付期限】原則と納期の特例の違いとは?
- 中途退職者に給与の源泉徴収票を発行する場合の4つの注意点
元予備校講師の経験を活かし、わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。
会計ソフトはクラウド推し。オンライン対応ももちろん可能です。
- 提供しているサービス
- 「税理士に確定申告をお願いしたい」という方へ
確定申告代行(決算込み) - 「わからない点を単発で相談したい」という方へ
単発スポット相談 - 顧問税理士はクラウド会計をお使いの方限定でお受けしています
クラウド会計税務顧問 - 税理士目線でクラウド会計の使い方をアドバイスします
クラウド会計使い方サポート
- 「税理士に確定申告をお願いしたい」という方へ
- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)
セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます