2017年5月から始まった「法定相続情報証明制度」。
2018年の4月からは「法定相続情報一覧図」の相続税の申告書への添付が可能になり、我々税理士にとっても身近な書類になりました。
この記事では、
「自分で相続登記や預金・株の名義変更をするために一覧図を取ってみたい!」
という方のために、「法定相続情報一覧図」を取得するまでの流れを、私自身の経験も交えつつまとめてみます。
この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。
詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ
相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています
単発スポット相談
当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。
当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。
ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)
このページの目次
法定相続情報一覧図を自分で取得するまでの全体像
「法定相続情報一覧図」を取るためには、いろんな書類を揃えた上で、登記所(法務局)に行って交付の申出をする必要があります。
一覧図が自分の手元に来るまでの流れをまとめてみると↓こんな感じです。
【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
↓
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
↓
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
↓
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
↓
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
以下、1つずつ見ていきましょう!
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
まずやらなきゃいけないのは、申出のために必要な書類の収集です。
ここで集めた書類に書かれている情報をもとに2の一覧図や3の申出書を作成しますので、これをやらなきゃ全てが始まりません。
どんな書類が必要かは法務局のホームページに以下のPDFデータがあがっています。
必ず用意する書類/必要となる場合がある書類 (PDF形式 : 151KB)
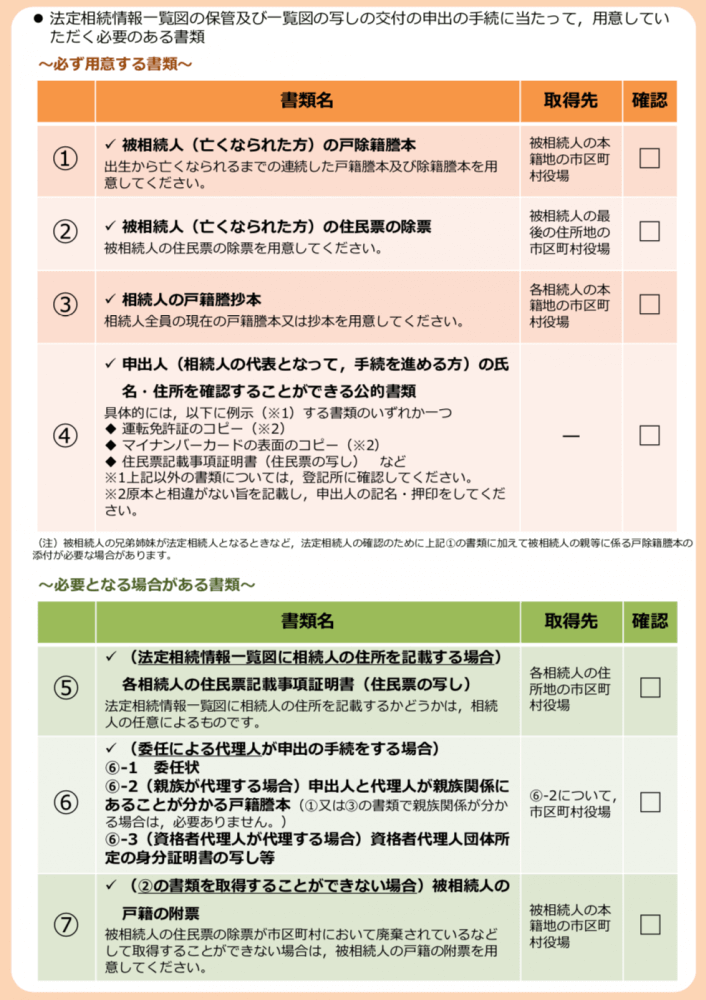
この内容を↓以下に載せてみると。
-
【必ず用意する書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本
(出生から亡くなるまでの連続したものが必要) - 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
- 相続人の戸除籍謄本
(現在の最新のものでOK) -
申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類
(運転免許証のコピー、マイナンバーカードの表面のコピー、住民票の写しなど) - (法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)
各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し) - (委任による代理人が申出の手続をする場合)
- 委任状
- (親族が代理する場合)
申出人と代理人が親族関係にあることがわかる戸籍謄本(①又は③で代用可) - (資格者代理人が代理する場合)
資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等
-
(②の書類を取得することができない場合)
被相続人の戸籍の附票
【必要となる場合がある書類】
このリストに基づいて、必要な書類を1つづつ収集していきましょう。
「自分で取る」という方の場合、①〜⑤(一覧図に住所を載せない場合は⑤は不要、②が無い場合は⑦)だけ揃えればOKです。
原本還付されるもの・されないもの
ちなみに、申出にあたって法務局に提出する上の書類の大半は、一覧図の発行が終わったらそのまま返してくれます。
(業界用語(?)では「原本還付」とか言ったりします。)
具体的には、①、②、③、⑤、⑦の書類は一覧図を受け取る際に一緒に返してくれますので、これらについては、ここで使ったあと他の相続手続で使う、ということも可能です。
…と、番号だけ言われてもピンと来ないと思いますので、上のリストに基づいて原本還付されるもの・されないものを整理してみます。
-
【必ず用意する書類】
- 被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本→原本還付される
- 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票→原本還付される
- 相続人の戸除籍謄本→原本還付される
-
申出人(相続人の代表となって手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類→原本還付されない
- 各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)→原本還付される
- 委任による代理人が申出の手続をする場合の書類→原本還付されない
-
被相続人の戸籍の附票→原本還付される
【必要となる場合がある書類】
というわけで、「④申出人の氏名・住所を確認することができる公的書類」と「⑥委任による代理人が申出の手続をする場合の書類(委任状など)」は原本還付はありませんので要注意です。
また、④と⑤の書類を1枚で兼ねることもできません。
私自身、申出人の方の④と⑤の書類を「住民票の写し」1枚で兼ねようとしたら、
「これは④の書類として預かるので原本還付できません。して欲しいなら、④の書類としてコピーしたものが別に必要です。」
と言われたことがあります。
(コピーはお願いすればその場で取ってくれます。ただしこれにも自署押印は必要です。)
亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけない!
と、ここまで話を進めてきた中で、おそらく↓こんなことを思う方も多いのではないかと…。

…亡くなった人の戸籍謄本、いるの??
はい、そうなんです(^^;
というのも、実は、法務局が発行する「法定相続情報一覧図」って、
「自分で作った一覧図に対して法務局が『これで正しい』とお墨付きを与えるもの」
なんです。
なので、次の2にあるように、元となる一覧図は自分で作らなきゃいけないですし、
それを作るために、そして、その作ったものが正しいものであると確認するためにも、亡くなった人の生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍謄本)は絶対に必要です。
つまり、これを使おうが使うまいが、亡くなった人の戸籍謄本はどのみち1度は取らなきゃいけないってことですね。
「亡くなった人の戸籍謄本を取らなくても済む便利な制度」
というわけではないので、その点誤解のないようにお願いします!
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
というわけで、上の1で必要な書類を集め終わったら、お次は一覧図を自分で作ります。
↓こんなのを作りなさいとのことです。
フォーマットは↓以下の法務局のホームページにたくさんあがっていますので、ご自身の状況に当てはまるものをダウンロードしてください。
主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局
1で集めた書類を確認しながら、正確に作成しましょう。
ここで作る図がそのままコピーされて「法定相続情報一覧図」に乗っかってきますので、記載もれや誤字脱字などは絶対にないように!
一覧図を相続税の申告書に添付する場合、一覧図は以下の様式を満たしている必要があります。
1:「一覧図」は列挙形式ではなく図形式のものであること
2:子の続柄が、実子・養子のいずれなのかが分かるように記載されていること
続柄は「子」で済ますのではなく、戸籍謄本に書かれているとおり(長男、長女、養子など)に記載することを忘れないようにしてください!
参考記事法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
さらに、法務局に提出する「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に必要事項を記入します。
申出書は以下のリンク先に様式と記入例があがっています。
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局
その際、氏名には資格名を忘れないように。
(私の場合だと「税理士 尾藤武英」といった具合)
また、申出人との関係は「委任による代理人」です。チェックマークの付け間違いにも要注意。
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
ここまできたら、お次は1〜3で揃えたり作ったりした書類を全て揃えて登記所(法務局)に提出します。
提出先の登記所は、以下の地を管轄する登記所のどれかを選択することが可能です。
- 亡くなった人の本籍地(死亡時の本籍を指します。)
- 亡くなった人の最後の住所地
- 申出人の住所地
-
亡くなった人名義の不動産の所在地
全国の登記所の場所などは以下のページ以降のリンクで調べることができます。
法務省:法務局・地方法務局所在地一覧
各法務局のホームページ:法務局
持参または郵送で書類を提出しましょう!
提出すれば↓こんな書類が渡されます。(窓口での受け取りを希望した場合)
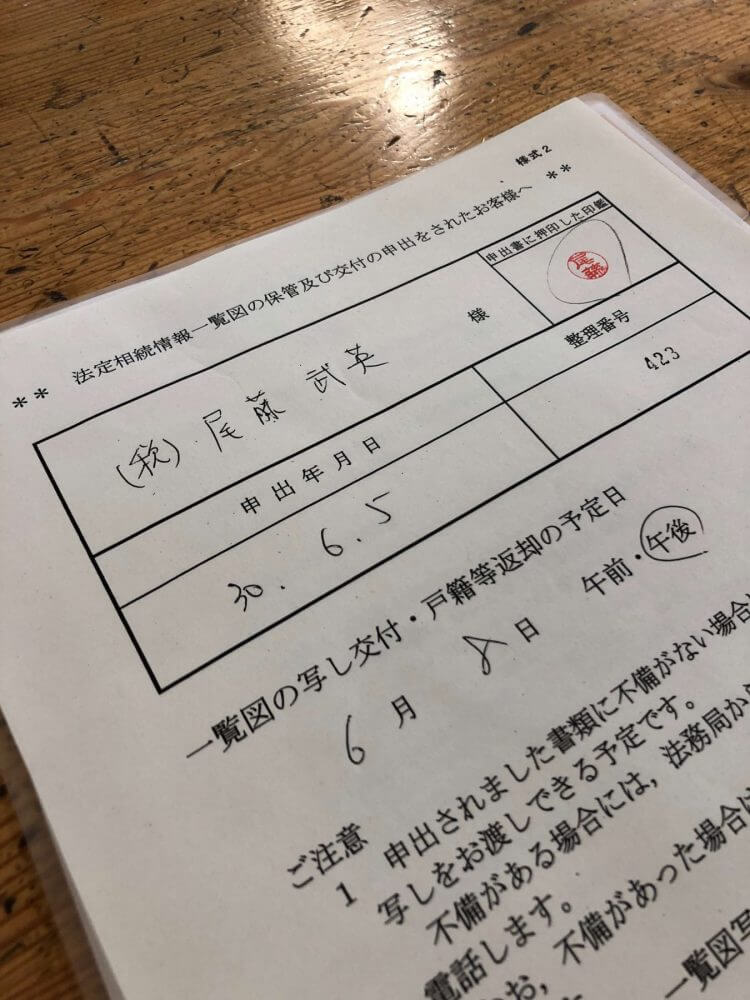
京都地方法務局の場合、だいたい3営業日程度で発行されることが多いようです。
場所によっては1週間以上かかることもあるようなので、日程に余裕を持って動くことをオススメします。
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
提出した書類に不備があれば登記所から連絡がきますが、それが無ければ「一覧図」は無事完成です。
指定された日時以降に受け取ることができます。
なお、窓口で受け取りの際は申出書に押印した印鑑の持参をお忘れなく!
(受取り時に受取書に自署押印する必要があるため)
また、郵送での受け取りを希望する場合は、返信用封筒と郵便切手の準備を忘れなく!
お疲れ様でした(^^
法定相続情報一覧図を自分で取得する方法のまとめ
最後に、一連の流れをもう一度まとめておきます。
【法定相続情報一覧図を取得するまでの流れ】
1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める
↓
2:法定相続情報一覧図を自分で作る
↓
3:「法定相続情報一覧図の保管および交付の申出書」に記入する
↓
4:1〜3の書類を登記所(法務局)に提出する
↓
5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る
慣れない方にとっては、
「1:戸籍謄本など、申出に必要とされる書類を集める」
と
「2:『法定相続情報一覧図』を自分で作る」
のハードルがやっぱり高いのかな、と思います。
(特に2の一覧図の作成が…でしょうか)
ただ、「自分で相続登記をやっちゃおう!」と考えている方なら、
集めなきゃいけない書類自体は相続登記の場合とほぼ同じなので、意外と抵抗なくできちゃうハズです。
この記事がそんなあなたのお役に少しでも立てば嬉しいです!
法定相続情報証明制度の具体的な手続について:法務局
【関連記事】
- 法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!
- 住所から地番を調べる方法【地番検索サービス+α】
- 地番から住所(住居表示)や土地の場所を調べる方法
- 相続税申告書の書き方は「相続税の申告のしかた」を見るのが便利
わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。
- 提供しているサービス
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ
相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています
単発スポット相談
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)
- 研修動画販売(相続税)
セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます
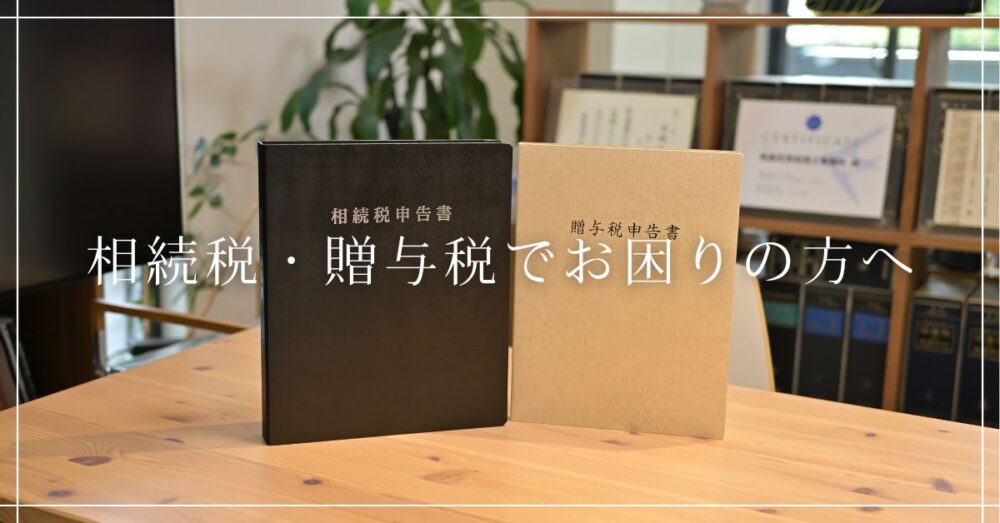

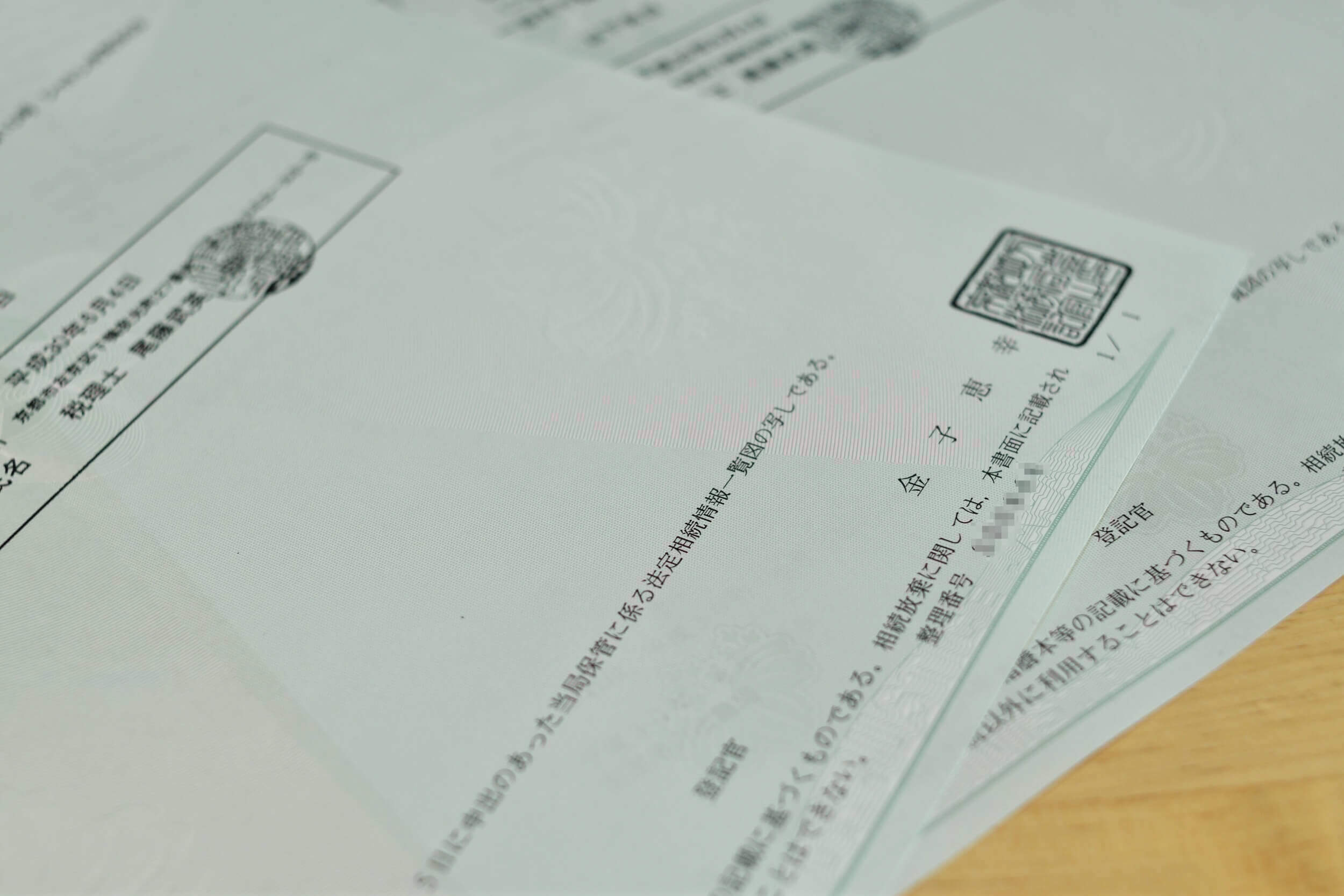
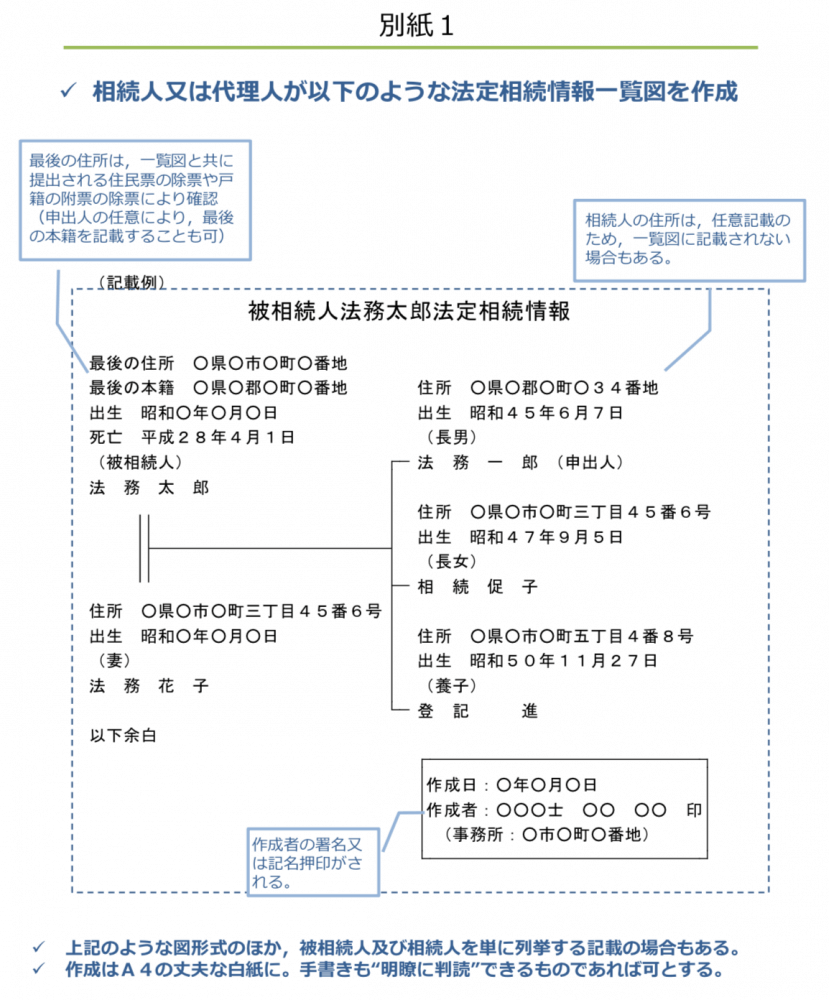
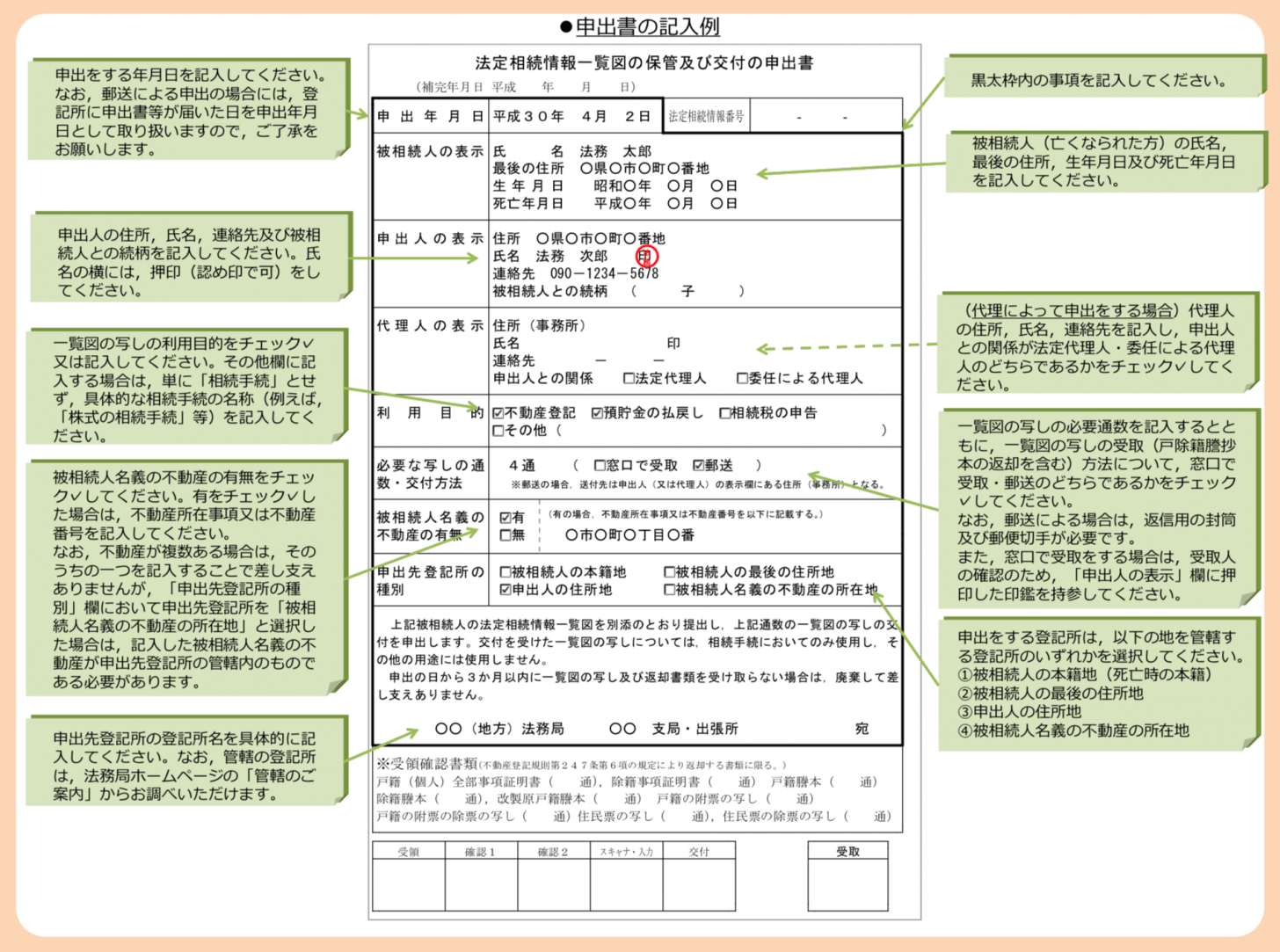
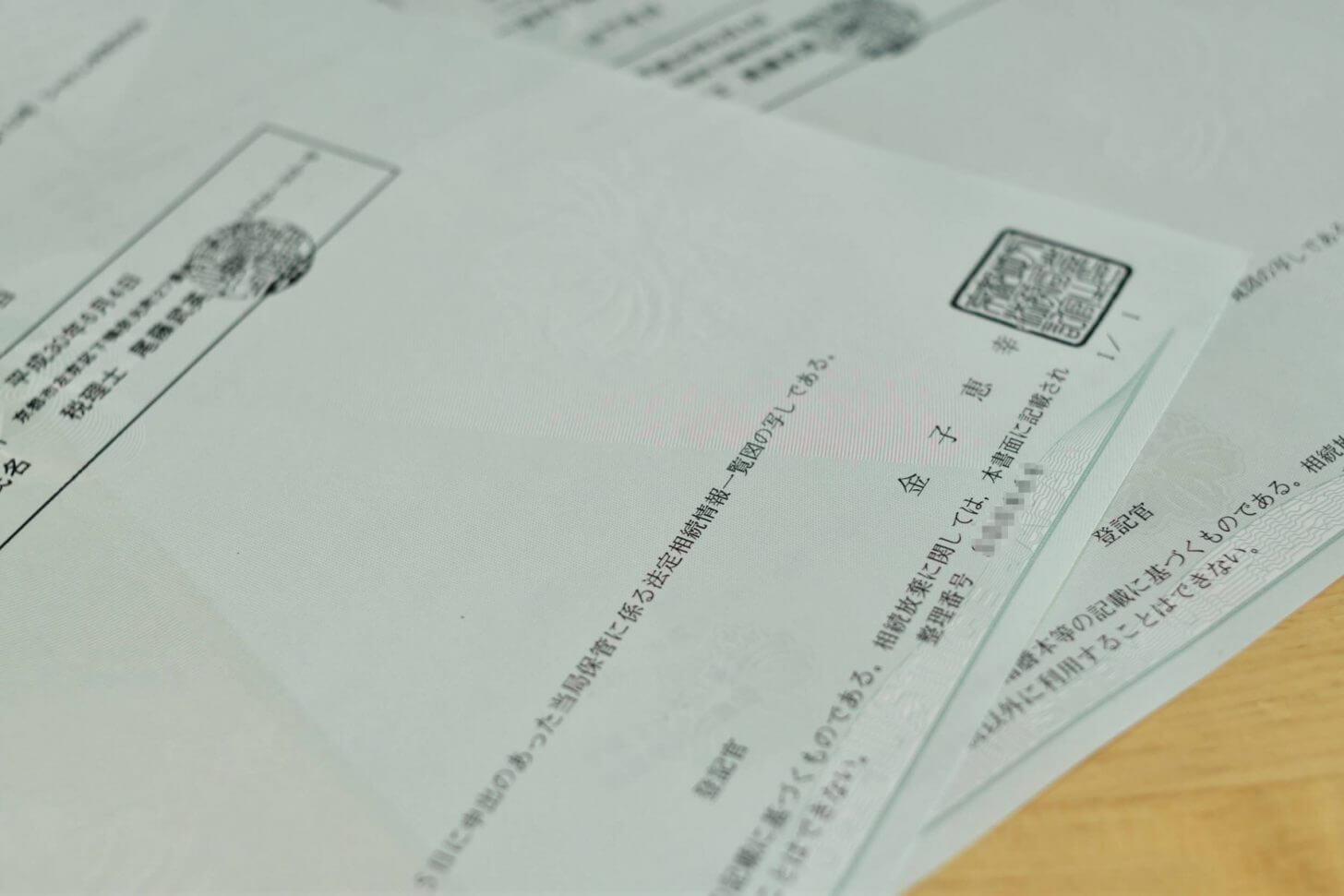
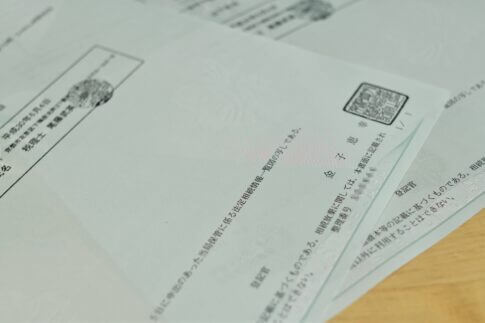
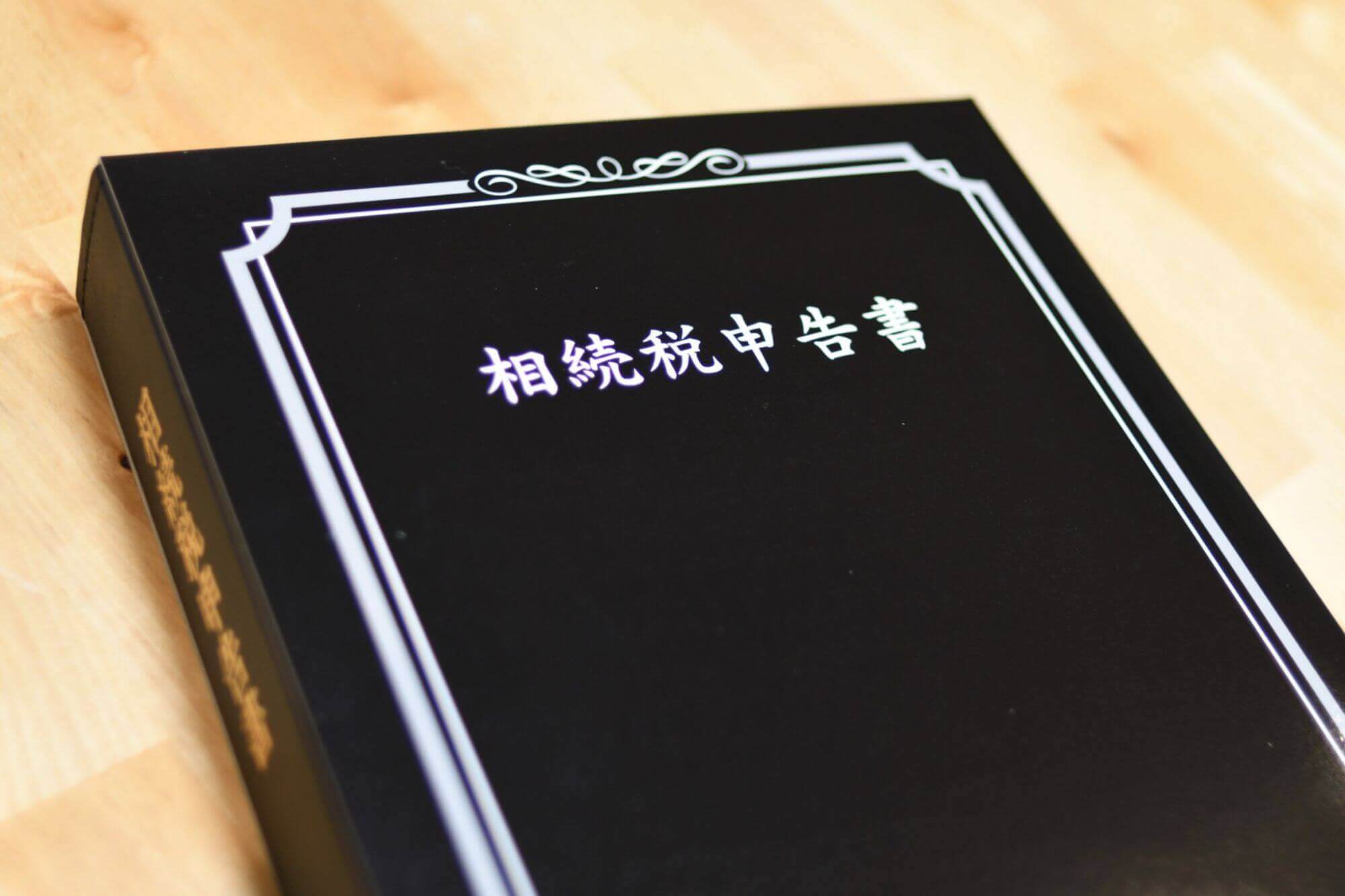
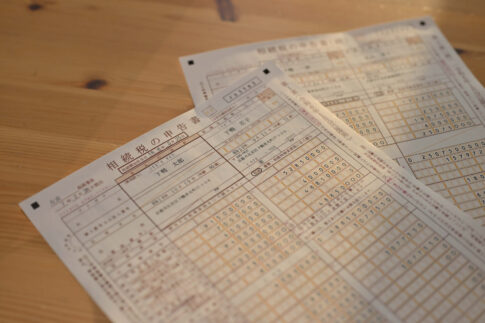
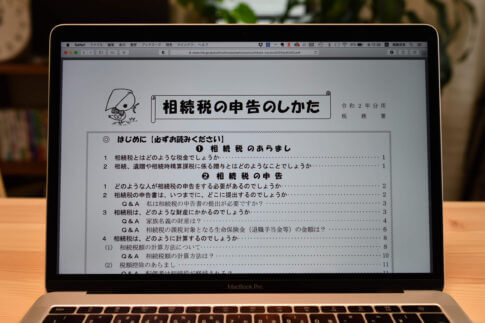
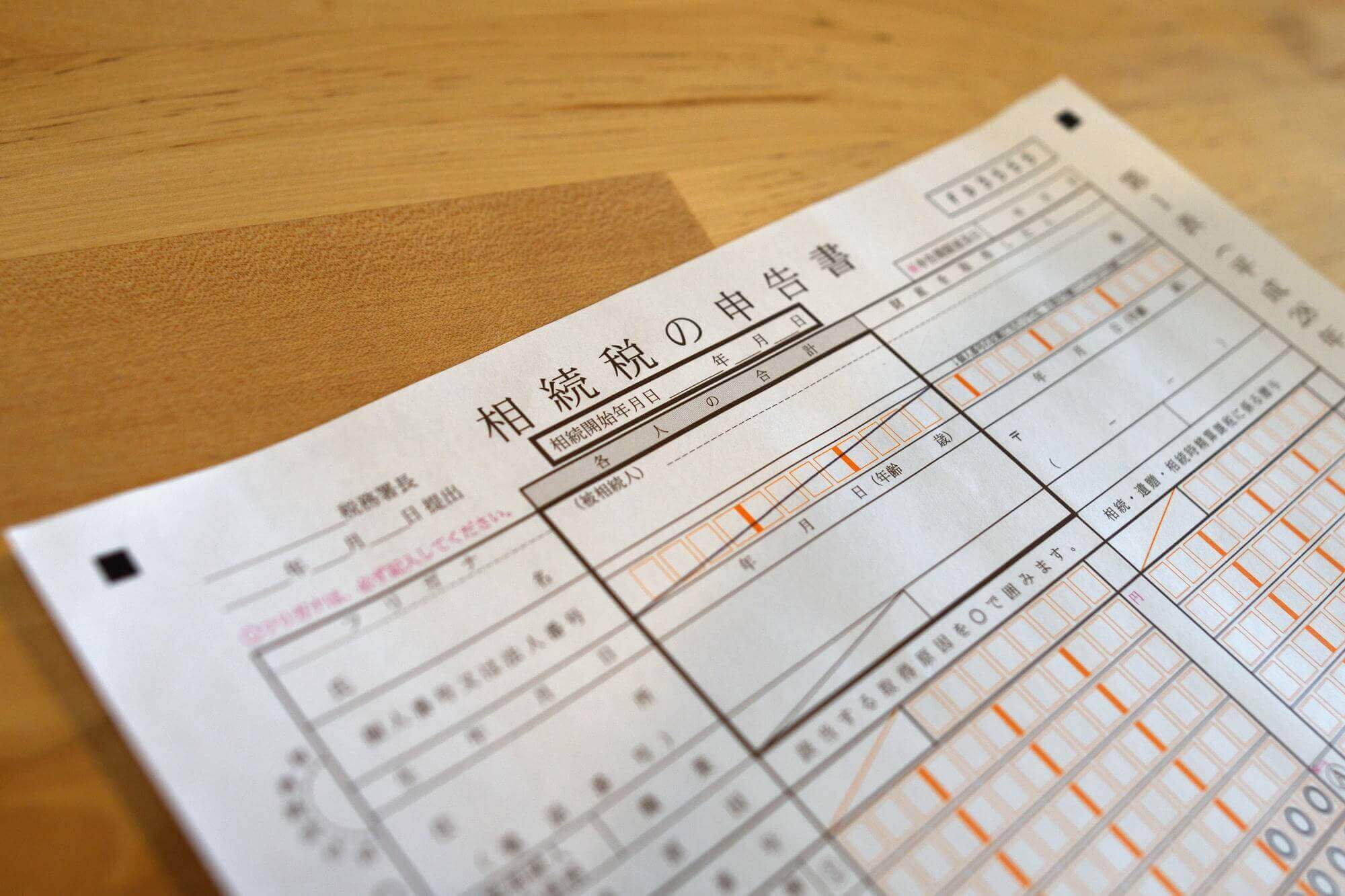
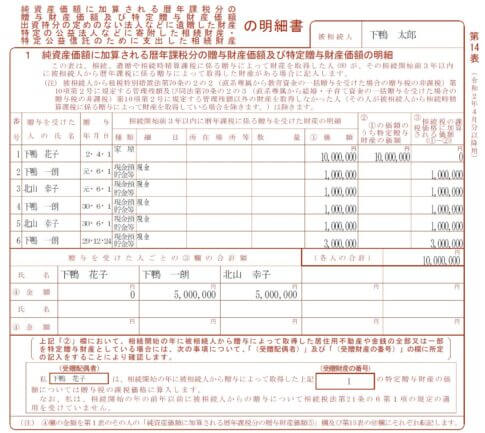
「法定相続情報証明制度って何?」など、基本的な情報は以下の別記事をご覧ください。
法定相続情報一覧図が相続税申告書に添付可能に!