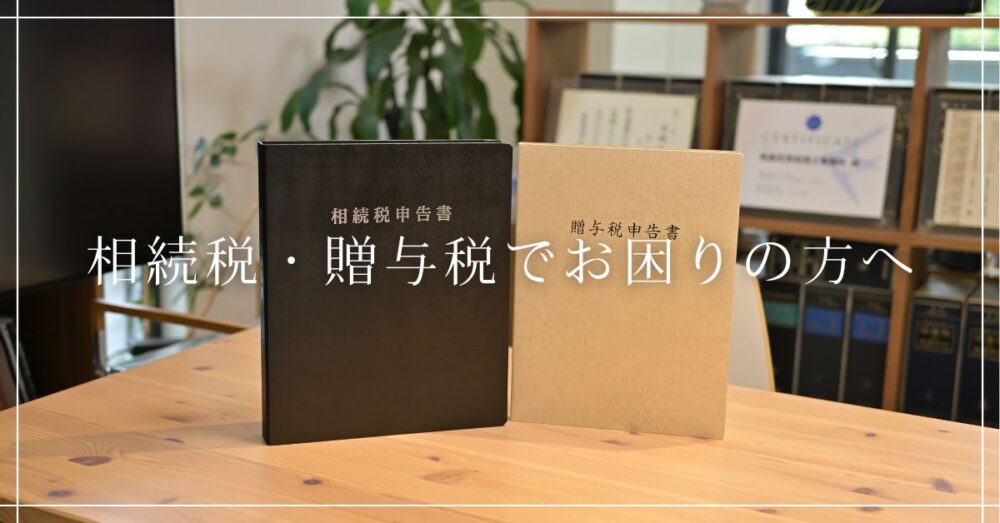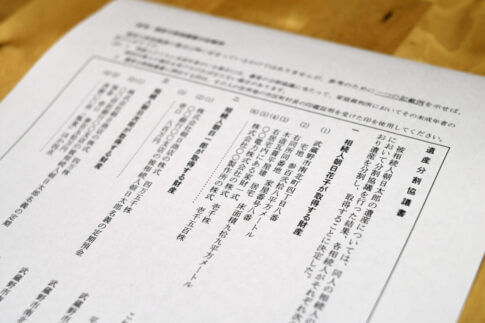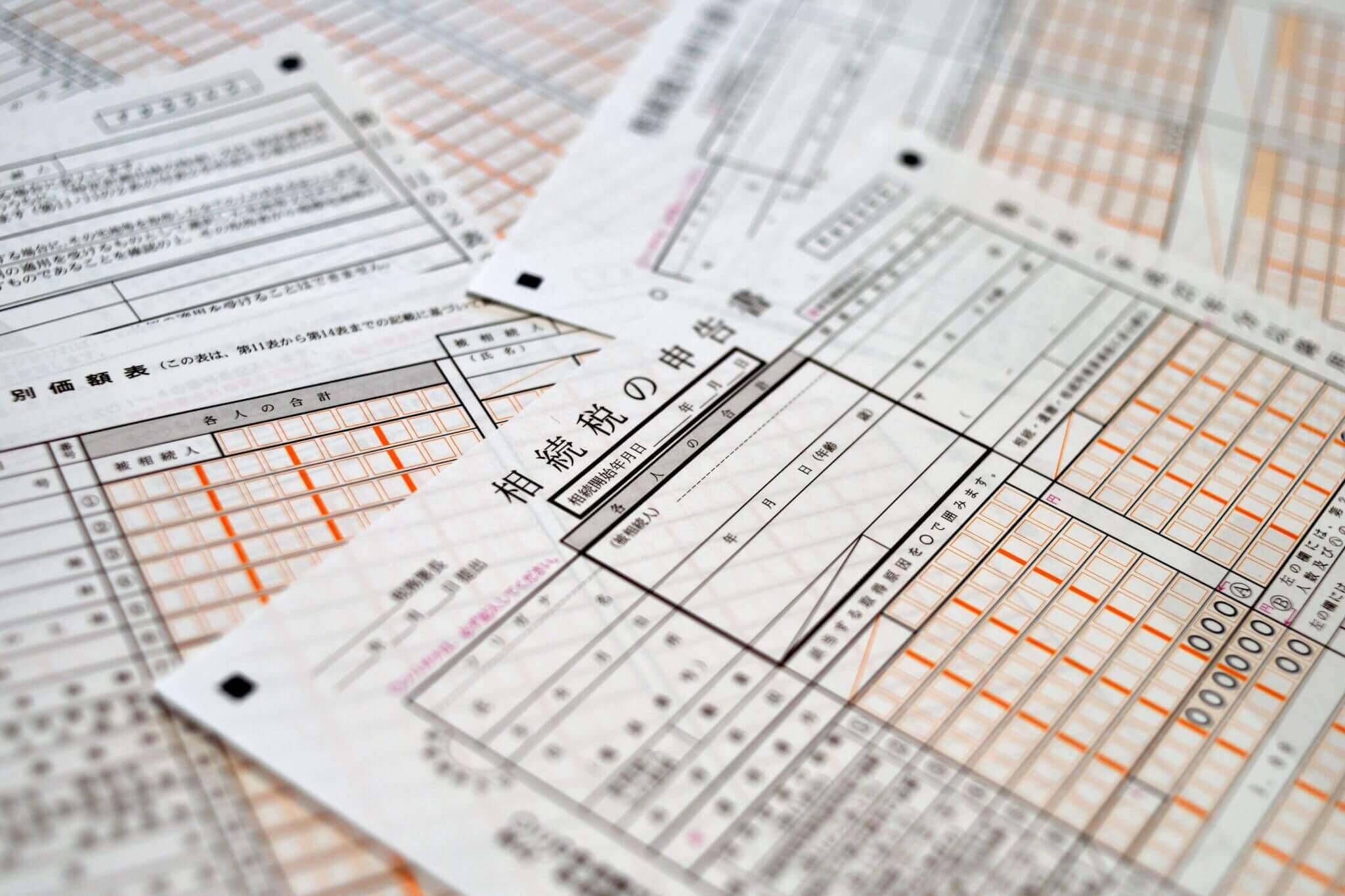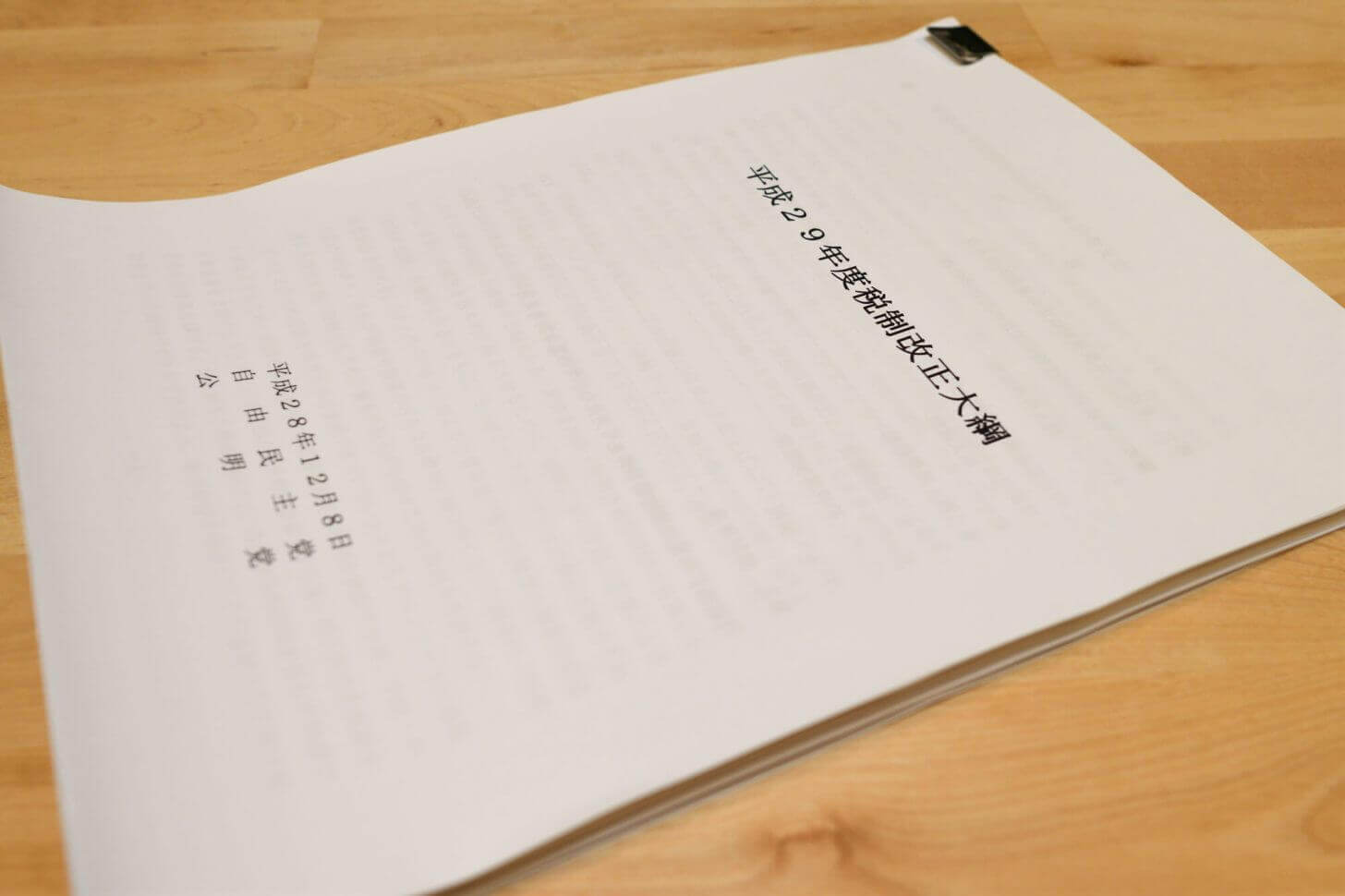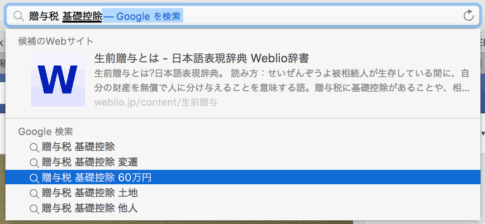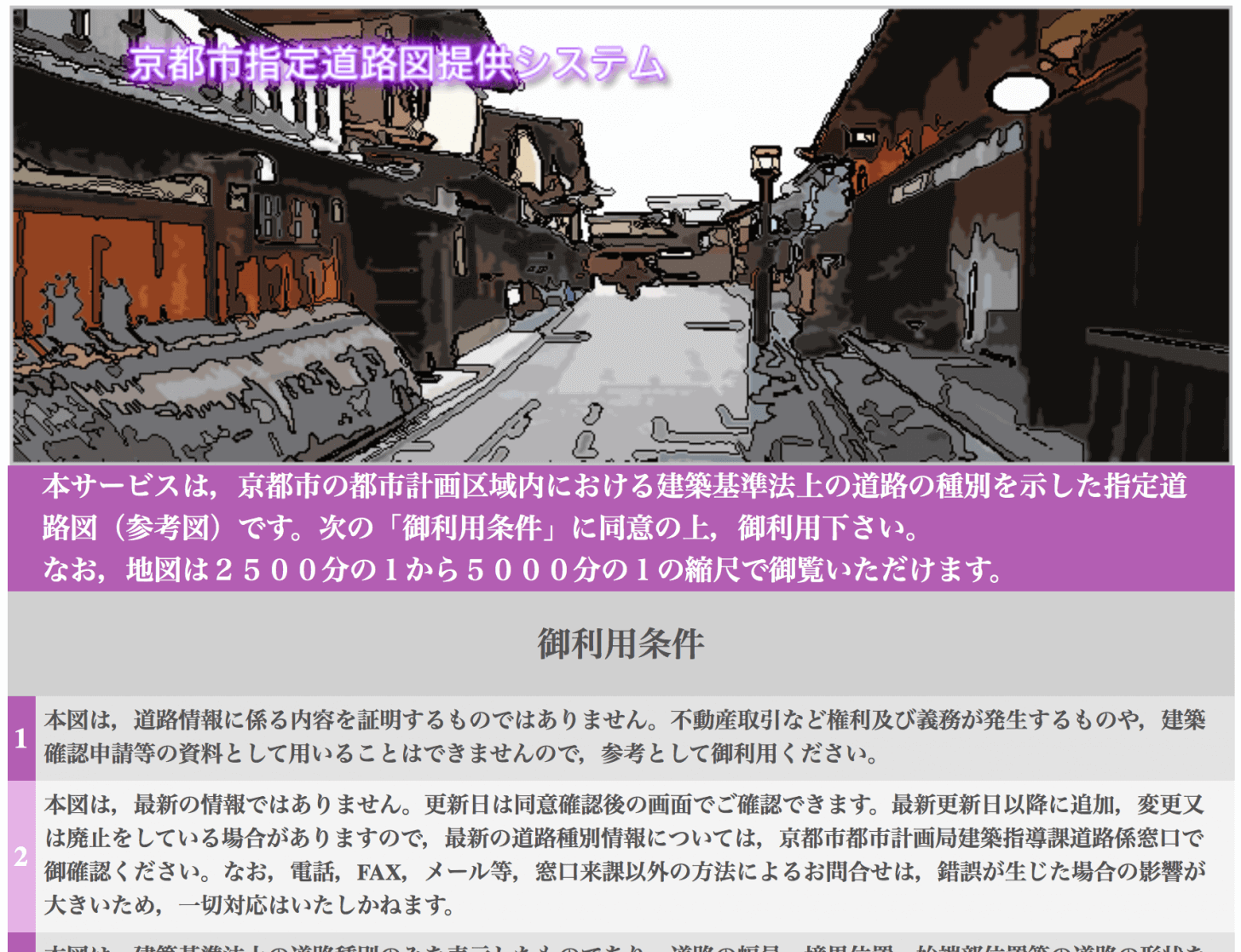昨日、最高裁判所で1つの判決がありました。
「相続税対策で孫と結んだ養子縁組が有効かどうかが問われた裁判で、無効とした二審の判断を覆し、『節税目的の養子縁組でもただちに無効とはいえない』との判断を示した。」
というものです。
節税目的の養子縁組「有効」、最高裁初判断 当事者の意思重視/ 日本経済新聞
日経新聞の今日の朝刊には
「この判断により、相続税対策で養子縁組を組む流れは今後さらに広がるだろう」
とのとある弁護士のコメントが掲載されています。
今日はこの判決を踏まえて、
相続業務に積極的に取り組んでいる税理士である私が普段から大切にしているひとつの思いを文章にしてみます。
この記事を書いた人

過去に税理士試験の大手予備校で相続税を教えていた経験から、相続税が専門分野。
事務所開業以来、相続税や贈与税の申告、相続税対策、相続税贈与税をテーマとした研修会の講師など、相続税に関する業務を多数行っています。
詳しいプロフィール(経歴や活動実績など)
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ
相続税シミュレーション(相続税対策) 単発のご相談もお受けしています
単発スポット相談
当ブログの運営目的は一般の方への正しい情報の提供であり、同業者等へのコンテンツ提供ではありません。
当サイトでは以下のポリシーに基づきコンテンツコピーの常時計測を行ない、盗用に備えています。
ブログ運営ポリシー(執筆編集方針、著作権保護のためのプラグインの使用etc.)
このページの目次
税理士として残念
まず、今回のこの判決について私自身がどう感じているのか。

です。
ただ、それは判決の内容に対してではありません。
何が残念なのかというと、上で紹介した記事の中にあるこの部分。
一審・東京家裁は、男性本人が縁組届を作成したとして有効と認定。二審・東京高裁は「税理士が勧めた相続税対策にすぎず、男性は孫との間に真実の親子関係を創設する意思はなかった」として無効と判断。孫側が上告した。
今回の争いの原因となった養子縁組は税理士が相続税の節税目的で勧めた、とある部分です。
もし相続対策の相談に乗った税理士が私であれば、今回の裁判はひょっとしたら起こってなかったかもしれません。
なぜなら、私であれば「養子を1人増やせば相続税が安くなりますよ」なんて無責任かつ怖いアドバイスはたぶんしないからです。
税理士に法律相談を受ける権限は無い
以前、税理士は遺産分割協議の内容に関わることはできない、と記事にしたことがあります。
過去記事税理士である私がお客様の遺産分割協議に関わらない理由
もちろん、税理士は「業」として申告書に添付する書類の作成が認められています。
そして、遺産分割協議書は相続税の一部の特例(小規模宅地等の特例など)を受けるにあたって申告書への添付が義務付けられている書類です。
なので、
「そんな遺産分割協議書を税理士が業として作成することになんの問題があんねん?」
と考えている税理士もいます。
しかし、そもそも論として、税理士に顧客から法律相談を受ける権限は一切ありません。
法律相談を受けることができるのは「法律家(弁護士や一部の司法書士)」だけに認められた権利。
いわゆる「非弁行為」は弁護士法違反にもなります。
(税理士以外の人が税務のアドバイスをすると税理士法違反になるのとほぼ同じ理屈です。)
なので、私は法律相談の範疇に入るようなデリケートなアドバイスは絶対に行わないと決めています。
遺産分割協議書の作成も、やったことがあるのはせいぜい相続人間で話し合って決まった結果を紙に起こす作業ぐらいです。
それぞれの財産の具体的な振り分けなどは全て当事者間だけで決めていただきますし、
もし「決められない」ということであれば、提携している弁護士を介して決めていただきます。
縁組をすることによって当事者はどう思うか?
確かに、養子を1人増やせば相続税の節税にはなります。
遺産の総額が2億円・相続人がお2人という方の場合、養子を1人迎え入れるだけで900万円ほど相続税が安くなります。
900万円は確かに大金です。
ただ、人によってはたかだか2億円のうちの900万円です。
「それだけのお金のために養子縁組なんて本当にやるんですか?」という見方はできないでしょうか。
養子縁組というのは自然にできた人の血の繋がりを動かす法律行為です。
当然のことながら、それを行うことで戸籍の記載事項にも変化が生じます。
養子になる側の立場で考えてみると、
- おじいちゃんおばあちゃんだと思っていた人が実はお父さんとお母さんでもあった。
- 自分にはお父さんとお母さんが2人ずついる。
-
お父さん(またはお母さん)だと思っていた人が実は兄弟でもある。
こうした事実を知ったときにそのお孫さん自身がどう思うのか。
また、養子を迎え入れるということは他の子供にとっては兄弟が1人増えるということを意味します。
兄弟が増えるということは、自分の相続分はもちろん減ります。
もし、自分が知らない間にそんな人間が1人増えていたとしたら、果たしてその人はどう思うのか。
(今回の裁判はまさにこのケースですよね。)
相続税対策として養子縁組を提案するのであれば、そうしたところにまでしっかりと考えを巡らせなければいけません。
もしそういう提案をするのであれば、
税金が安くなるというメリットだけではなく、そうしたリスクも当事者全員に直接きっちりと説明して、全員の了解を得た上で実行に移すべきでしょう。
3つの柱が並び立ってはじめて「相続対策」は成果をあげる
ひとことで「相続対策」と言ってもそこには3つの柱があります。
- 相続税を減らすための対策
-
相続税の納税資金を確保するための対策
-
遺産分割でもめないための対策
そして、忘れてはいけないのは
です。
これら3つの柱が全て並び立ってはじめて「相続対策」は成果をあげるのです。
もし養子を増やして相続税額が安くなったとしても、
今回の裁判のように、それが原因で相続人間で争いが起きてしまったのであれば、
それは「相続対策」としては完全な失敗だと思っています。
相続対策として養子縁組を勧めるのであれば、
将来絶対に(←100%の確率で)もめないような状況を作り上げるべきですし、
私の力ではそれは絶対に不可能なので、私ならそんな提案は怖くてできないかな、と…。
そうすることで税金が安くなることはわかりきっていても、です。
その相続対策、必要ですか?
税金さえ安くなれば何を提案しても許されるのか?という疑問は他の相続対策でも感じる部分です。
たとえばよくある↓こんな話。
「相続人が3人の場合、1億円の現金を相続税評価額6,000万円の賃貸物件に変えれば相続税が630万円から120万円と500万円以上も安くなります!」
それって本当におめでたい話なんでしょうか。
だって、500万円税金を安くするために数千万円もの財産が目減りしているわけですよね?
しかも、残っているのは遺産分割がやりにくくて処分もしにくい賃貸物件。
その3人の誰がその不動産を引き継ぐんでしょうか?まさか共有にする?
てか、そもそも誰もそんな物件なんて欲しがらないかもしれませんよ。
資産が現金から賃貸物件に変わったことで、
相続人間でそんな不要な争いが起きてしまうかもしれません。
だったら、1億円から630万円の相続税を払って残りのお金をみんなで分けた方が全員にとってハッピーなんじゃないですか?
税理士だからって税金だけが安くなる方法さえ提案しておけばいい(しかもそれで多額の報酬も…?)というのは違うと思っています。
税理士だって1人の血の通った人間のハズ
「税理士だからといって税金のことだけを考えていてはいけない」
この言葉は相続業務を行う税理士(と税理士事務所の職員)は特に肝に銘じなければいけません。
税理士は単なる「税法の専門家」であり、弁護士をはじめとする「法律家」では決してありません。
そして、税法の専門家の前に1人の血の通った人間です。
「こんな提案は税理士の領分を超えているんじゃないだろうか。」
「自分が同じ立場だとして、果たしてこの提案は受け入れられるんだろうか。」
私はそんな気持ちを大事にしながら日々相続業務を行なっています。
【関連記事】
- この記事をきっかけに寄稿させていただきました。
税理士新聞2017年2月25日号に寄稿しました - 税理士である私がお客様の遺産分割協議に関わらない理由
- 社会の構成員として。ルールやマナーは守る&そんな手助けとなる仕事を
- 仕事で厳守を心掛けている3つのこと。期限、時間、そしてお金
わかりやすいアドバイスでお困りごとを解決します。
- 提供しているサービス
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
相続税・贈与税の申告 - 将来どれぐらい相続税がかかるか知りたい・相続対策をしたい方へ
相続税シミュレーション(相続税対策) - 単発のご相談もお受けしています
単発スポット相談
- 相続税や贈与税の申告が必要な方へ
- 事務所の特徴(強みや大切にしていること)
- 研修動画販売(相続税)
セミナー研修講師や執筆のご依頼もお受けできます